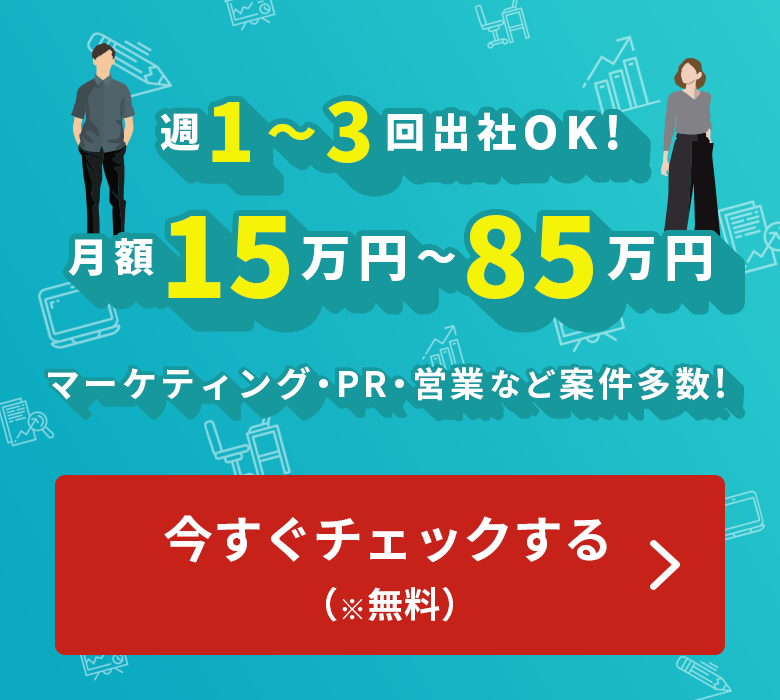投稿者: 「本音採用」ライター

これまで、週1〜4回出社というフレキシブルな働き方で、フリーランスや起業家、子育て中のキャリアウーマンを中心にプロとしてのお仕事をご紹介してきたCARRY ME。先日11月28日に、初のリアルイベント【CARRY ME Night vol.1】をアーティストの副業・社会進出を支援する「YAYAY!」と共同開催しました。
当日のCARRY ME Night vol.1のプログラムを公開!
- CARRY ME代表大澤からのご挨拶
- アイスブレイク(近くの席にいる方と名刺交換・自己紹介)
- 日本アーティスト協会「YAYAY!」代表宇田川より活動紹介
- CARRY MEで活躍しているプロお二人のキャリアとスキルを解剖!
- Q&A
- 交流会
それぞれについて、ご紹介していきます。
日本社会の働き方を変えるムーブメントに!CARRY ME代表大澤の思い

これまでの日本の主流の雇用形態であった正社員での採用は、そのまま会社に在籍し続けることで多くの人が収入が上がるような仕組みになっていましたが、その分「会社」に縛られて仕事をすることになります。それが必ずしも今の日本で幸せな形とは限りません。育児や介護といったライフステージの変化によって正社員のステージから降りざるを得なくなった時、キャリアが狭まってしまう、あるいは無くなってしまうという事態に陥ります。
しかし、これからはキャリアの選択肢がひとつしかないという世の中から、個人が専門スキルを持ちキャリアの選択肢を持てる世の中にしていくことが必要です。ある場面で「正社員」以外の業務委託をはじめとする新しい働き方を選択しても、その後業務委託、プロ経営者、正社員として再就職などと自分のライフステージや志向に合わせて働き方を主体的に選んで行ける社会がこれからのスタンダードになることは、働く私たちにも企業側にもメリットがあるのではないでしょうか。
というのも、日本ではまだ米国より外部人材の活用が進んでいないのが現状です。米国では9割以上の企業で外部人材を活用しているのに対し、日本ではクラウドソーシングを含めても2割弱にとどまっています。業務委託の求人数はここ数年増えてきており、少しずつではあるが働き方が柔軟な方向へシフトしてきています。が、この流れをさらに加速させなくてはなりません。
そのためには「働き方・キャリアの選択肢(オプション)を増やす」という活動を大きなムーブメントにしていくことが必要です。
そのためにも今回のようなリアルイベントも定期的に今後開催・SNSでの拡散を通し、この活動の認知度を上げていきたいと考えています。
アーティストの社会活用を推進!「YAYAY!」宇田川の取組み

共同開催の日本アーティスト協会「YAYAY!」代表 兼 CARRY ME採用コンサルタントの宇田川からは、ミュージシャンをはじめとするアーティストの現状課題と「YAYAY!」の取組みについて説明がありました。
自身も「ガリバー宇田川」としてメジャーデビューを果たした現役ミュージシャンであり、様々な仕事を経てCARRY MEの採用コンサルタントの肩書きも持つ宇田川。宇田川自身も、アーティスト活動をしている人間のキャリア形成の難しさを身をもって経験している一人です。ですが、これからの数年のうちに、多くの経歴を持っていることや正社員以外の経験を持っていることもキャリアチェンジのマイナスと考えられなくなる時代が来るのではないかと言います。
「YAYAY!」ではフリーランスとして活動するアーティスト、特に知名度は低いもののプロダクトの質や成果が保証できる「職業アーティスト」と言われる中間プロ層を可視化・育成し、企業や組織とつなぐ機会を創出するマッチングと、ブランディングとPR活動に力を入れて活動をしています。
CARRY MEの採用コンサルタントと同様、この新しい仕組みで、アーティストの社会参画・セカンドキャリアの創出を盛り上げたいと語っていました。
CARRY MEで活躍しているプロのキャリアとスキルを徹底解剖!
CARRY MEで活躍しているプロはどんなスキルの共通点があるのか?

今回ご登壇頂いたプロの方はこちらのお二人です。
白幡健太郎さん。大学卒業後、広告業界に従事。消費財メーカー、地方自治体や外食産業、大手通信会社、アトラクション施設などのデジタルコミュニケーション戦略の立案からディレクションを多岐業界に渡り担当。2018年8月に独立。知財を活用したBtoBサービスの開発とウェブ解析・デジタルPRのコンサルティングを両軸で行っています。現在CARRY ME経由で2案件獲得。

高橋ちささん。正社員として10年以上PRに従事後、出産を機に2017年夏からフリーへ。IT業界やBtoB向けサービスの広報・PR支援を得意とし、新サービスや既存プロモーション、広告戦略、イベント企画、メディアアプローチまで手掛ける。日経新聞、日経ビジネス、東洋経済オンライン、ダイヤモンド、Yahoo!ニュースなど、メディア取材獲得件数多数。CARRY ME経由で3案件獲得。
お二人の強みの共通点として大澤があげたのは、
- 需要のある職種であること、かつ、スキルの掛け合わせでニッチな人材となっていること
- 契約先の話を聞く力、コミュニケーション力の高さ
- 企業が業務委託のプロを採用するメリットでもある「先方スタッフの育成」ができること
の3点でした。こうしたスキルがあるためにお二人はCARRY MEでも引く手あまたのプロとしてご活躍され、複数案件で稼働しているのです。ここからは、お二人への質疑応答を絞って公開!上記の3つの共通点を重ね合わせてお二人の回答を聞くと、フリーランスとして仕事を獲得し続けている理由がわかりました。
正社員からフリーランスに転身。不安をどのように打ち消す?
大澤:お二人とも正社員を経験後フリーになられたということで、正社員のままでいた方がいいのではないか、などといった不安はありましたか?また、不安を打ち消す方法などを具体的にお伺いしたいです。

高橋さん:私の場合は、前職のPR会社が子育てをしている女性社員が一人もいない職場だったんですね。結婚して子供が生まれたら、その会社で仕事をしながら子育てをしていくイメージが全く湧かなかったというのがフリーランスへの転身を考えたきっかけです。
また、正社員で働いている時は裁量を全然任されていなくて、自分がどれくらい市場でやっていけるのか試してみたいと考える時期がありました。そこで、報酬は頂かないで知人のお手伝いをしたりとか、ボランティア的にアドバイスなどをして少し自分の力を試し始め、「これならやれるかも」と思ったタイミングで会社と交渉して副業をスタートしました。
その後「副業でもある程度お金を頂ける」と感じた段階で正式に独立をした形です。
ある程度リスクをヘッジしながら、徐々に始めていったという感じですね。
白幡さん:高橋さんに近いところがあって、僕も「独立しよう」「フリーランスになろう」というつもりはあんまりなかったんです。ただ、自分でやりたい事業があって、在籍していた会社で正社員として就業しながらとなると物理的に難しかったので、事業が出来る方法を考え始めました。
フレキシブルに働けて収入が確保できるような働き方というところでフリーランスを選びました。不安を除くためにしてきたこととしては、決められた期間にこれだけ貯めるという目標を定めて貯金を頑張ったことと、いつまでにこのくらいの仕事を取ると決めて、フリーランス用のポートフォリオを作成しました。その中でCARRY MEさんと出会いました。
高橋さん:白幡さんに質問なのですが、その時は結婚されてたんですか?
白幡さん:結婚していましたね。
高橋さん:そこも含めてリスクは感じなかった?
白幡さん:感じ・・・ましたね。そこで、現状の生活費にいくらかかっているのかを全部洗い出して、最低限この辺りの保険を全部解約して、このくらいあれば死なないというライフラインのコストを引いたことと、ローン関係は正社員のうちに全部必要なものは申請をして、もし何か会った時は契約できるつてを用意しておきました。
大澤:奥さんのご両親からフリーになるときに猛反対を受けたと伺いましたが?
白幡さん:そうですね(苦笑)。
そのくらいの世代の方だと、どんな仕事であれフリーランスっていう働き方自体がわからないという感じですね。正社員でい続けることが安定という考えの方は多いと思うので。
その会社で一生やっていくのが安泰だろうという風には思われていたみたいなんですが…。でも今の時代は少し違って、同じ会社にずっとい続けることの方がリスクといいますか、そういったことをお話ししたりして認めていただいた感じです。
同じ組織で働き続けることのリスクとは?市場で必要とされ続けるために

大澤:今、同じ会社で働き続けることがリスクというお話がありましたが、具体的にはどういった点が正社員でい続けることのリスクだとお考えですか?
白幡さん:正社員自体を否定しているわけではないのですが、同じ所で仕事をすると仕事内容のガラパコス化が進んじゃうんですよね。そこの上司から気にいられるような仕事の仕方だったり、その会社でしか通用しない仕事の仕方になってしまう。
僕は会社を辞めようと思った時に今のままではいざ市場に出た時通用しないなというのがぶつかった課題だったんです。会社員時代にこれが絶対に正義なんだろうなと思っていたことが実は全く真逆で時代遅れで、アップデートされていなくて、これじゃ報酬は入らないっていうレベルだったんです。これではダメだなと思って、まずは実際自分がしてきた仕事の棚卸しを始めました。
その上でこれとこれを組み合わせればニーズもあるしニッチな仕事だからやっていけるなというのを1回だけではなく、何回も検討してアップデートして、第三者にも見てもらって、テストをしてきたという感じですね。
高橋さん:白幡さんのような考えの方は、意外にずっと正社員でもやっていけると思うんですよ。というのも、フリーランスになってもそういう考え方はあって、現状のスキルやキャリアや経験だけではきっとフリーランスでは通用しなくなって来る。
しかも社員ではないのできっと早い段階で仕事が貰えなくなって来るというシビアな現状があります。ですので常に自分の市場価値とか世の中のマーケティング状況を見ながら自分ができる範囲でのスキルアップとか方向転換は考えなきゃいけなくて、それはフリーランスでも正社員でもおそらくやらなくてはならないことなのかなと。
白幡さんは正社員の時からそういった考えがあってフリーランスになったとおっしゃってたんですが、おそらく正社員のままでもその考えであればやっていけるのかなという気がします。なので、雇用形態は関係なく、自分がこの業界でいつまで現役で働けるのかということを考えて、自ずと何年か先を考えながらアップデートしていく必要があるのかなと思います。
案件獲得のために必要なことやCARRY MEの活用法を公開!
大澤:お二人にお伺いしたいのですが、これから案件を獲得したいと思っている方に、どのようなアドバイスをされますか?CARRY MEの活用や、心構え、付けるべきスキルなど、なにかありましたらお願いします。
高橋さん:私自身、フリーランスになったタイミングでは自分の報酬をどのように決めたらいいのかというところから分からなかったので、その点からCARRY MEさんには相談して、広報支援の一般的な月額報酬を聞いて交渉に入って頂いたりとか、かなり込み入ったところから相談させて頂いていたように思います。
自分のキャリアを相談しつつ、こういう仕事が欲しい、ないしは今後こんな風になっていきたいのでどうしたらいいかという相談もしました。具体的には昨年、仕事をしていく中で自分の出来る範囲でしか仕事を受けなくなってきてしまったんですよね。
よく言われてますが、キャッチボールできる範囲でしかボールのやりとりをしなくなってきたので、筋肉がすごく弱くなってきているような、遠くまでボールを飛ばす練習が全然できなくなってきているように感じていました。
何かやる事に対してもすごくリスクを感じるので、自分ができる範囲のことでしか受けられない。こういった場合、後何年、この引き出しが空になるまで働けるのだろうかと考えた時に不安になったので、そういう相談もCARRY MEの方にしました。
それで色々アドバイスも頂き、チームで働けるような案件や常駐の形でお仕事していくのもいいんじゃないかというお話をあそこにいる毛利さんにアドバイス頂きまして、そういう仕事をご紹介いただいて、現在お仕事をさせて頂いています。完全に自分で仕事を取って来るということではなくて、CARRY MEさんを活用できるのであれば使い倒すじゃないですけど、パートナーとして色々と相談されてみてもいいのかなと思います。
白幡さん:そうですね…CARRY MEさんに登録する前にやってたこととしては、ひたすら某転職サイトを見ていました。そこはスキルのタグ分けをした上で報酬が確認できるんですね。そこからどのスキルを持っていると高い給料が貰えるっていうのをひたすら分析していて。
その中で自分ができるものってなんだろうと考え、自分の棚卸ししたスキルとマッチングさせて磨いていったらもっと報酬は高くなるかなと仮説を立ててスキルを上げていったというところですね。
とはいえ、フリーって仕事をもらう時にどうやって仕事をもらったらいいか分からないし、先ほどの高橋さん同様、報酬もどのくらいを付けたらいいか分かりませんでした。
CARRY MEさんに登録してどうやって交渉したらいいか、どうやったら揉めずに自分の報酬を上げて契約を成立させられるかなどご相談し、すごい今満足いく状況下でお仕事させていただいているので、すごい感謝しております。
Q&A
フリーランスへの転身にあたり、意識すべき思考法は?
大澤:こちらは事前に頂いたアンケートからの質問ですが、会社員からフリーランスになる際意識の持ち方などを変えないといけないと思いますが、どんなことを意識していましたか?
高橋さん:フリーランスであれ正社員であれ経営者であれ、自分のアップデートを怠らずに業界のマーケティング動向をみながら市場価値を高めていくと言うことを意識したほうがよろしいのかなと思います。
私はPRをやらせてもらっていますけれども、PRに今後必要になるスキルというのが色々出てくるんですよね。その中の出来る範囲のものを自分も取得していかなくては長くは続かないだろうなというのは感じます。そこはどんな職種であれ同じなのかなと思います。
白幡さん:高橋さんのおっしゃったことと似ていて、キャッチアップ能力かなというように思います。エンジニアでフリーランスの方とお話するんですが、例えば書いたことのないコードをかけますか?って言われて「出来ません」って言ってしまう人はフリーランスに向いていないんですよね。
嘘になっちゃうかもしれないけど「出来ます」って言って、そこからの何ヶ月かの間である程度のところまで勉強していく人が勝手にアップデートできている人なのかなという風に思います。
大きい声では言えませんが僕も出来ないことがあったとしても「多分大丈夫です」って言う感じでもらって、そのあとすぐに調べたり知人に会ったり本を読んだりして何かしらのアップデートをして実務で出来る部分があればそこに参加させてもらって備えるということを意識してやってますね。

交流会も開催!フリーランスのネットワーク構築とCARRY MEスタッフとの相談の場に!
最後に交流会の様子を少しご紹介します。交流会では、CARRY MEのスタッフに直接相談や質問をする参加者の方の姿が多くみられ、また、ほかの参加者の方と名刺交換やコミュニケーションを取りながら交流を深めていました。

今回のようなリアルイベントを通じフリーランスの皆さんのネットワーク形成の場になったり、新しい働き方への理解を深める機会にしていきたいと考えております。今回ご紹介してきた新しい働き方がこれからの日本のスタンダードな選択となれる世の中の流れを作るべく、今後も定期的にリアルイベントの開催する他、CARRY MEが運営するメディア「プロ採用4.0」、SNS等で発信して参ります。ご興味のある方、応援頂ける方はぜひ下記のSNSへのフォローをお願いいたします!
次回のイベント決定次第、SNSでご紹介していきます!
CARRY MEで仕事を獲得したい方はこちら:会員登録する(※無料)
Facebook :https://www.facebook.com/carryme.jp/
Twitter: https://twitter.com/carryme_tw
**本記事で掲載したお写真はカメラマンYasu Iijimaさん、藤野いち子さんが撮影してくださいました!素敵なお写真をありがとうございました!

営業職人材をヘッドハンティングする際にも、もっと効率的に、できるだけ優秀な人材を採用したいと考えることはありませんか?そういった願望を抱くヘッドハンターのみなさんは、
「今の現状に満足いく結果を得たい」
「労力ばかり使う手当たり次第のヘッドハントでは限界がある」
「コネクションに限界を感じている」
そういった課題を抱えたことがあるからこその願望が生まれてくるのでしょう。今回は、そんな悩める課題に対して、マルッと解決できる「優秀な営業をヘッドハンティングするための5つのコツ」を徹底的に解説していきます。
まずはよそ見をせずにこの記事で解説していく5つのコツを抑えていきましょう!
ヘッドハンティングに必須!営業職人材の頭の中を覗いてみよう
優秀で魅力的な営業職人材のヘッドハンティングを成功させるために、彼らの頭の中を知ることはとても重要な要素の一つです。
優秀な営業職人材がヘッドハンティングをされたときにどこを重要視するのかを知っているかどうかで、その採用が成功するかどうかが決まってしまう場合もあります。
そんな優秀な人材の頭の中を覗いてヘッドハントする決め手の材料をこの章で掴んでいきましょう。
これまで仕事で知り合った人からの誘い
自分のことを全く知らず、また本人も知らないところから、突然ヘッドハンティングを受けたとしたら、ものすごく条件がよかったり、たまたま自分のしたいことができそうな環境がすぐに提示でもされない限り、即断られてしまうでしょう。
これには以前営業職についていた筆者にも経験があります。某有名女性誌において自分の仕事ヒストリーの記事が掲載になったときのこと。掲載後に勤務先に直接電話があり、ヘッドハンティングの誘いを受けました。電話の主からはその記事を読んだこと以上のことは伝わってこず、いい印象を受けませんでした。唐突とも感じさせられるヘッドハンティングは、ヘッドハンターからの情熱や熱意を感じられないとうまくいくことはないように思います。
もし、ヘッドハンティングしたい相手と直接のコネクションを持っていなくとも、知り合いの紹介など、様々なつてを使ってコンタクトをとることも有効です。そのためにも、ターゲットにしたい人材がいる会社や、業界とのコネクションにはつねにアンテナを張っておくことが重要です。ターゲット人材にたどり着くまでのコネクション構築の努力を重ねれば、直接会って話ができる確率も数段あがることでしょう。
現状よりも収入や待遇、働く環境が良い
自分自身の仕事環境の現状に、完全な満足を得ている人はどれほどいるのでしょうか。収入は高いが業務内容に不満を持っている人、業務内容は満足いくものだが収入に不満がある人、収入にも業務内容にもそこそこの満足を持っている人、両方に強い不満のある人など、人により様々な状況があることでしょう。ヘッドハンティングしたい人材が、いまどのような状況で、どのような条件で働いているのかをよく考えてみましょう。
そして、ヘッドハンティングしたい人材の企業の年収や条件も調査してみましょう。優秀な人材への資金が潤沢にあるのであれば心配ありませんが、もしそうでは無い場合には、ヘッドハンティングを成功させることは難しいかも知れません。しかし、諦めずに業務内容の良さややりがいをしっかりアピールできるようにしましょう。
近年の働き手は、仕事を給料だけの尺度で判断することはありません。働きやすさ、職場の雰囲気、独自の工夫や環境など、なにが好印象をもたらすかはわかりません。ヘッドハンティングを受けたいと思わせる職場環境作りや業務内容の確かさを追求していきましょう。
社内キャリアがイメージできる
優秀な人材は、モチベーションが高く、常に自分を切磋琢磨しています。よって、自分自身が成長できる環境を常に求めているともいえます。新しい職場でのチャレンジがヘッドハンティングしたい人材にとって有益であると感じさせる具体的ポイントをもうけることができたならば、ヘッドハンティングも成功につながっていきます。彼・彼女の現状をよく理解し、さらなる高みを提示できるようにしましょう。
営業職で優秀な人材をヘッドハンティングするのが難しい理由
そうはいっても、営業職で、目立つほどの実績がある人材をヘッドハンティングするのは至難の技です。飛び抜けて優秀な人材は業界内で有名になってしまい、ヘッドハンティング業界のコンサルタントやリサーチャーなどがもつ独自のネットワークに知られることになってしまいます。資金豊富な大手企業などに早い者勝ちでヘッドハンティングされてしまうからですね。
また、リサーチャーもターゲットを見つけたら、まわりに知られないようにリサーチをかけているために、ふと気づいたときにはもうヘッドハンティングが進行してしまっていた、ということもあります。
突出した実績がない人材でも、コンスタントに安定した水準で売上をキープしてきた人材も、評価が高くなりヘッドハンティングされやすい傾向があります。そのような人材はどんな企業にとっても重要な人材であり、良い待遇を受けている場合も多く、なかなかヘッドハンティングを成功させようとしても難しい面があります。
ほか、優秀な営業を新たに採用しようと人材会社を使って採用のためのチャネルを増しても、優秀な人材は自ら動かずとも採用されていく面もあるため、転職やヘッドハンティングに消極的です。募集をかけても必ずしも求めているような人材が応募してくれるわけでもありません。しかし、優秀な人材が新たな転機をもとめて応募してくれる場合もありますので、就業募集の機会をオープンにしておいてもよいでしょう。
営業職のヘッドハンティングを成功させる5つのコツとは?
実現するには難しい面も多いヘッドハンティングですが、どのようにすすめていけば成功させられるのでしょうか?
営業職人材の採用理想像を具体的に
多くの人材から選びたい気持ちもあるので、人材像を広く抽象的なイメージにしておいて、採用していく方がたくさん候補者とも会えますし一見効率的に見えます。
ですが、実際は欲しい人材像のイメージをできるだけ絞り厳選して採用活動を行う方が逆に効率的なヘッドハンティングができるのです。
人材像を絞る際には、職場の雰囲気をがらっと変えるようなカリスマ的な人物を求めているのか、商品知識豊富な物静かなタイプを求めているのか性格部分や気質部分で絞り込みをかけてもいいでしょう。
プライベートも大切にするため時間を有効に使える人材を求めているのか、いまの会社に足りない要素のある人材を加えるのか、仕事の進め方で絞り込みをかけてももちろんOKです。大切なのは、軸をぶらさずに採用したい人材像を明確に手元に用意してよそ見をしないことですね。
参考記事:採用マーケティングとは?メリットや手順・フレームワークを徹底解説!
業界内の動向を探り、異業種交流会など参加する
求める人材像を具体的にしたら、そのような人材に出会えそうな場所に出向きましょう。それがWeb上にあるのであれば、そこに登録して人材を探しましょう。そして実際にオフ会や交流会を企画して出会う可能性を作り、コネクションを構築していきましょう。
大切なのは、Webでもリアルでも、どんな人が集まる場所なのか、その場所に集まる人の属性とニーズを考えて候補者を検討することです。
LinkedinやFacebookなどのSNSで探す
オフ会や交流会に参加したり、探すことに抵抗や手間を感じる場合は、まずLinkedinやFacebookなどから、マッチする人材を探してみましょう。
特にLinkedinは、仕事のコネクション構築に大いに役立ちます。所属している企業や専門業務内容を知ることができます。転職を今希望していない人材でもその人材について詳しく閲覧できるため、非常に効率よく有能な人材を探すことができるツールです。積極的に利用してみましょう。
正当に評価していることを伝える
ヘッドハンティングしたいと思う人材への調査や理解を怠っていては、絶対にヘッドハンティングは成功しません。本当に採用したい人材に出会えたら、相手のこれまでの実績を理解して評価し、ヘッドハンターの誠意をきっちりと見せましょう。本気で行った対応には相手も答えてくれるはずです。
自社への客観的な理解を深めPDCAを回せる型を作る
優秀なヘッドハンターは自社の理解を徹底的に行って、瞬時に良い面・悪い面が言える状態にあります。「自社の理解なんか、コーポレートサイトを見ればいいから全員一緒でしょ?」そう思う方も少なくありませんが、実は違います。
あなたの自社への理解と実際に現場で働いている人の声は異なります。あなたも現場で働いている一員ではありますが、採用したい職種の現場をリアルタイムで把握しているわけではないはずです。だからこそ、採用職種の現場への理解を深めるために、アンケートを取ってリアルな現場の風土や特徴を理解することに努めましょう。
できるなら、定量的なデータ、定性的なデータの両方を取れるようにしておき、定量的なデータを使って視覚的に分かりやすい図を載せた資料を作り、定性的なデータをもとにヘッドハンティングするときのトークに活かすとPDCAが回しやすい環境を作ることができるためおすすめです。
どの企業も、ビジネスで生き残り成長していこうと、必死に有能な人材を確保しようとしています。ヘッドハンティングを成功させるため、この記事で紹介した事を意識してみてください。優秀な人材との相乗効果で、ビジネスを盛り上げていきたいものです。
企業・採用担当者の
みなさまへ
CARRY MEでは、年収600-1000万円レベルのプロ人材を
「正社員採用よりもコストを圧倒的に抑えながら」
「必要な時に、必要なボリュームで(出社もOK!)」
「最短1週間の採用期間で」
ご紹介いたします。

アウトソーシングとは
アウトソーシングとは、企業が担う業務(仕事)を外部の専門業者に外部委託することを指すビジネス用語です。
一般的にアウトソーシングされてきた業務例として、
○事務・経理処理の補助的業務
○荷物の梱包・配送業務
○店舗運営管理
などが挙げられます。
近年では、人事や法務といった高度な専門知識を有するコーポレート部門の業務(仕事)を委託するケースや、変化も大きく専門知識も必要なIT関係の業務でもアウトソーシングされるケースが増えてきました。
これまでは自社のノウハウは他社に流出しないよう自社社員の育成と業務の引き継ぎでまかなわれてきましたが、昨今ベンチャー企業の増加でそうしたノウハウのない会社が外部と契約し人材育成を含めたアウトソーシングを行うというケースもあります。また、主流となっているM&Aやジョイントベンチャー、業界内の事業提携も広義的にアウトソーシングを位置づけることができます。
アウトソーシングの市場規模と必要な背景
経済産業省が発表している資料では、アウトソーシングの1種であるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の国内市場規模が、2009年の1兆4936億から2015年には1兆6000億まで増加していると指摘されています。
アウトソーシング市場の増加の原因は、若年労働者人口の減少です。少子高齢化に伴い、日本の労働人口が減少しているのはみなさんご存じの通りです。経済産業省の発表した「第4次産業革命への対応の方向性」では、雇用人員判断を示すD.I(過剰-不足)が、2013年以降はマイナス(人材不足)に転じており、2016年には大企業・中小企業、製造業・非製造業、全規模産業全てにおいて、マイナス(人材不足)を記録しています。
これらの状況が何を表しているのか。
社員として人材を確保しようにも、募集が集まらなかったり経験が不足している人材しか集まらないようになるという問題を企業は抱えています。アウトソーシングはそうした人手不足の補完戦略として、プロを契約で招いて業務を行ってもらったり、更に進んで自社の既存人材の育成を行ってもらうなど、コストをかけずに成果を出すための重要な経営戦略と位置付ける企業が増えていることも考えられます。
【参考】経済産業省 平成26年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(2)国内BPO市場の規模
【参考】経済産業省 第4次産業革命への対応の方向性
アウトソーシングに向いている職種、業種
まずアウトソーシングに向いているとされる職種や業種についてご紹介していきます。
アウトソーシングを行うケースには大きく分けて3つあると筆者は考えます。
①自社でノウハウを蓄積できないような専門性の高い業務をプロに外部委託するケース
②自社社員を社内の重要業務に当たらせるために補佐的な業務を外部委託するケース
③事業展開を広げたり業務の効率化を図るために、外部委託するケース
これら3つのケースの具体例をみていきましょう。
高度な専門技術をアウトソーシングするケース
人事・法務・会計・情報システム関連の業務をプロ(例えば税理士や会計士、弁護士などの士業や人事経験の長いプロ人材)に委託する場合が想定されます。
補佐的業務をアウトソーシングするケース
事務・受付業務(総務・経理)などで派遣社員さんなどに委託するようなケースが想定されるのではないでしょうか。また、大きな店舗やイベント会場などでの運営スタッフの業務も主催者側の指示に従って補佐的業務をするので、ここに当たると言えます。
事業展開を広げる・業務効率化のためアウトソーシングするケース
いわゆるフランチャイズ契約や販売代行契約などで店舗運営を他社人材に委託するケースが考えられます。また、業務の効率化という点でアウトソーシングする例としては、物流業務や資材調達業務を自社で抱え込まず他社に委託し購入する形をとることもあります。
類似業務から見るアウトソーシング
ここでは、アウトソーシングと類似の業務との違いを示すことでアウトソーシングの特徴を明確にしていきましょう。
アウトソーシングとBPOの違い
アウトソーシングは、自社の強みや基幹部分を担う業務(仕事)を自社の従業員が担当し、その他の業務(仕事)は専門業者に外部委託することが形態をとります。しかし、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)は本来のアウトソーシングよりも委託業務範囲が広く、基幹部分の業務(仕事)も含む全ての業務(仕事)を外部委託することを可能にした新しいアウトソーシングの形態です。
アウトソーシングとシェアードサービスの違い
シェアードサービスとは、M&Aや分社化によって増えたグループ企業のコーポレート機能(人事部、総務部、法務部、データセンターなど)を一箇所に集約し、コストの削減及び業務(仕事)の効率化・品質向上を図る経営手法を指すビジネス用語です。
先述したBPOを含むアウトソーシングでは外部人材に業務委託するのに対し、シェアードサービスはグループ企業内で業務を集約するので内部の人間が業務を行うというところが大きく異なります。
アウトソーシングと派遣の違い
いわゆる派遣と呼ばれる人材派遣とは「派遣元となる派遣業者に登録している者を、派遣先となる事業所へ派遣して、かつ派遣先の指示命令のもとで労働サービスを提供する雇用形態」のこと。
それに対して業務請負(アウトソーシング)とは「請負契約(当事者の一方(請負元)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(請負先)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約)に基づき、製造、営業など業務を一括して請け負う形態」。
派遣は雇用契約なので労働に対して対価が支払われますが、アウトソーシングは業務請負契約なので、成果物に対して対価が支払われます。極論すれば、派遣は成果がでなくても賃金が発生し、アウトソーシングは成果がなければいくら働いても対価を支払わなくてもいいということです。
アウトソーシングのメリット
アウトソーシングのメリットは大きく3点あります。
1)コスト削減
自社で人材を雇用し、育てて即戦力とするには大きなコストと時間がかかります。アウトソーシングすることで、そうしたコストを削減することができます。また、アウトソーシングが繁忙期のみでいいのなら、それ以外の時期に余剰人材(コスト)がでることもありません。
2)スピーディーな競争力向上
特に専門性の高い業務や変化の激しいITなどの専門業務において、自社既存人材でその情報を学び続けるのにはかなりの労力が必要です。その点、アウトソーシングをすればその分野に明るく即戦力のある人材が業務に当たってくれるので、スピーディーな競争力の向上が期待されます。
3)品質、アウトプットの質の向上
日本の多くの企業では、プロであるよりジェネラリストであることが求められる風潮が強かったため専門業務についてはそのプロには敵いづらいという弊害があります。その点、その分野の専門性のある組織や人材にアウトソーシングすることで、商品やサービスといったアウトプットの質の向上が見込まれます。
適材適所で、アウトソーシングを活用していけば上記のようなメリットを得ることができます。そのような賢いアウトソーシングにするには、どんなコツがあるでしょうか?次の章で考えていきます。
賢いアウトソーシング活用の成功秘訣
どんなにメリットが多いからといっても、単にアウトソーシングを使って自社スタッフが楽をできておしまい、ではアウトソーシングをしっかり活用できたとは言い難いですね。
そこで、アウトソーシングを賢く活用していくための秘訣を3つご紹介していきます。
1)社内ノウハウが蓄積できる仕組みを考える
せっかくプロにアウトソーシングをしても、そのプロでしか出来ない業務になってしまってはずっとアウトソーシングし続けなければなりません。
結果的にコストアップとならないよう、アウトソーシングをした個人や組織と良い関係作りをし、必要なノウハウは自社で蓄積できるように仕組みを整えましょう。
例えば委託先に自社社員の教育を依頼し、自社社員が得てほしいスキル、そのレベルなどを委託先と共有し定期的にチェックするといった、フローを作るのも効果的です。
2)ガバナンスの弱体化対策を行う
外部人材が業務に関与することで企業内の統制がとれなくなったり、企業としての一体感が醸成されなくなる、いわゆるガバナンスの弱体化が起こるリスクがあります。ガバナンスの弱体化は業務を行う上での責任感やモラルの低下を招くこともあります。委託業務の目的や内容の明確化を行って進捗管理を定点で行うことが対策として考えられます。
3)情報漏洩のリスク対策を行う
アウトソーシングをするということは自社スタッフ以外の人間が自社の情報を使って仕事をするということです。当然リスクのひとつとして情報漏洩の問題があると認識しておく必要があります。
アウトソーシング先への規制やルール創りはもちろんのこと、それをチェックするフローと定期的なフローの見直しが求められます。また、セキュリティなどの必要環境を整備することも効果的です。
アウトソーシングの導入方法
最後に、具体的にアウトソーシングを導入するにはどのような方法をとると良いかご紹介していきます。
具体的な導入手順は下記の5つの工程に分けられます。
1)現状の業務棚卸
現在自社内で行っている業務内容を分解し、どんなタスクがあるのかを棚卸しましょう。
2)工数の可視化
棚卸したタスクを更に分解していきます。作業レベルを掘り下げ、工数を可視化することが大切です。
3)アウトソースできるかできないかの分別
工数を可視化できたら、それらをアウトソースできるか、またはアウトソースするべきか検討し、分別します。
4)アウトソースできる業務で守りたいものの定義(QCDどれをどのぐらいの品質で守りたいか)
アウトソーシングする業務が明確になったらQDCの視点からアウトソーシングしてもらう上での納品レベルを定義しておきましょう。QDCは、「Quality(品質)」「 Cost(費用)」「Delivery(引渡)」の頭文字をとったもので、主に製造業から使われ始めた製品の納品状態をチェックするポイントです。ひとつひとつポイントを確認しておくと、
「Quality(品質)」
納品してもらう業務の品質、レベルについてです。人材育成までしてほしい、ですとか、作る資料においても社内向けか外部向けかでそのレベルは大きく異なるはずです。
「 Cost(費用)」
どのくらいのコストをかけるのか?アウトソーシングする業務とその対価として支払う費用のバランスがとれているか?
「Delivery(引渡)」
依頼した期日までに納品されるか?適時、適所への納品がたもたれるのか?
と言うものが挙げられます。これらをはっきりさせておくことでアウトソーシングする際の指示が明確になります。
5)アウトソースできない業務の理由を明確化
最後にアウトソーシング出来なかった業務の理由をはっきりさせておきましょう。これを行っておくことで、アウトソーシング業務を増やすことになった場合、上記のような選択プロセスの短縮が可能です。
導入手順に必要な作業は、業務棚卸や工数の可視化、アウトソースできない業務の理由を明確にするなど少し骨の折れることもあります。しかし、こうした作業を行った後にうまく依頼先を選べばその業務の周りに起こる課題から的確に抽出し体制や施策を一緒に考えてくれるプロ人材を配置することも可能です。社内の人間だけでで考えるとなかなか進まないということもあるので、アウトソーシングという形を検討し、ぜひ一度外部のプロ人材を導入を始めてみることをお勧めします。
(企画・構成 松澤 唯/ライター 渡部梓)
企業・採用担当者の
みなさまへ
CARRY MEでは、年収600-1000万円レベルのプロ人材を
「正社員採用よりもコストを圧倒的に抑えながら」
「必要な時に、必要なボリュームで(出社もOK!)」
「最短1週間の採用期間で」
ご紹介いたします。

個人事業主の加入保険、理解していますか?
個人事業主の皆さん、保険に入っていますか?
保険に加入していても個人事業主になるときに最低限の保険の変更手続きをして以来、見直していないという方もいるのではないでしょうか?
もしもの時の保障になる保険。
本業で忙しいとつい疎かになりがちです。
しかし、会社員とは異なり、個人事業主が加入する社会保障は保障内容が会社員より薄く、もしもの備えが不足しがちであると言われます。
また保険について考えることは自分が個人事業主として働く上でのリスクの棚卸しにも非常に有効な手段です。
この記事では、多くの個人事業主が加入している保険を紹介し、検討すべきリスクのポイント・保険の選び方をご紹介していきます。個人事業主のみなさんのリスクヘッジに是非お役立てください。
個人事業主の保険と保障内容
多くの個人事業主が加入するベーシックな「公的な社会保障」は次の2つと言えます。
- 国民健康保険
- 国民年金
日本では、「国民皆保険」と言われるように、何らかの保険に加入することが求められます。
どちらも、会社員が加入する社会保険や公務員が加入する「共済保険」などに加入条件が合わない場合に加入する非常にベーシックな保険と考えることができます。
では、国民健康保険で保障される内容はどんなものがあるのでしょうか?
国民健康保険で保障される内容
- 医療費の自己負担分以外の保障
- 高額医療費(1か月の治療費が一定額を超えると超過分を保障)
- 出産育児一時金(出産時に42万円を保障)
という点が主なものです。
一方、国民年金の保障内容は下記のとおりです。
国民年金で保障される内容
- 老齢基礎年金(60歳または65歳から支給される、いわゆる年金)
- 障害基礎年金(国民年金加入中に1・2級の障害になったとき支給)
- 遺族基礎年金(国民年金加入中に死亡した際に支給)
- 寡婦年金(夫死亡時に受け取る)
- 死亡一時金
が主なものと言えます。
会社員の方が保障は手厚い!
個人事業主になるときに、「社会保障は会社員の方が恵まれている」という点は何となく理解していたという人は多いと思います。
しかし、具体的にどういった点が「会社員の方が恵まれている」のか、ご存知ない方もいるかもしれません。
そもそも「会社員や公務員が加入している社会保険と、個人事業主が加入している国民健康保険では社会保険の仕組みが違う」ということをおさえておかなければなりません。
たとえば年金制度では、フリーランス・自営業の方は「国民年金」のみ(1階建て、と言われます。)の構造です。
一方会社員・公務員の方は、それに「厚生年金」がプラスされています(2階建て)。
また、会社員や公務員の方は、会社と保険料を折半しているので、同じような金額の保険料を払っている人が同じような保障を得る状況になったとしても、受け取れる年金・保障の額が大きく異なります。
受け取れる額が大きく異なるのは、年をとってから受け取る老齢年金だけではありません。万一本人が亡くなった場合に配偶者等に支給される遺族年金や、障害1級・2級などの認定を受けた場合に支給される障害年金も、すべて同様です。
また、個人事業主は雇用されているわけでもないので、雇用保険で対象になる保障も受けることができません。
例えば、育児休業中や病気やケガで休職している際の手当金の支給が会社員にはありますが、個人事業主にはありません。
このように、個人事業主が国民健康保険・国民年金加入で保障できている内容は、会社員や公務員より薄いと言わざるを得ません。
保険を検討することはリスクを考えること
会社員の方が保障が手厚い事はわかっても保険加入を考えると何から手をつけてよいかわからない。
そんな思考停止状態に陥りがちです。
ここでおすすめしたいのが、いきなり加入すべき保険について考えるのではなく、
今の自分の環境と、将来起こる可能性のあるリスクを先にリストアップすることです。
保険加入を考える上で一番大切なのが、リスクを検討することです。
ここを疎かにすると感覚で保険を選択することになり、結果的に的はずれなものになってしまいます。
自分の現在の環境とリスクがしっかり認識できていれば、加入する保険は自然と決まっていきます。
①自分の環境のリストアップ
- 家族構成
- その家族に扶養義務が現在発生しているか
- 自分が日常的に世話をしなくてはいけない家族がいるか(子育てや介護)
- 自分の仕事内容
などを詳しく検討しましょう。
例えば、金銭的にはパートナーの収入をメインに生計を立てているものの、自分が育児や介護をメインで担いながら仕事をしているという方がいるとします。
この方の場合は、自分が働けなくなる時に育児や介護の担い手がいなくなる問題をどのように解消するのかがポイントになります。
また、仕事によっては出勤出来ない時点で収入がストップする人と、リモートなどで収入が見込める場合があります。
どんな場合が自分にとって収入が断たれる状況になるのかが想像しやすいように、自分の仕事内容の棚卸しも必要です。
②自分の今の生活が維持できなくなるリスクをリストアップ
次に、保険でカバーするかしないかは一度脇に置いて、自分の今の生活が維持できなくなるリスクをリストアップしていきましょう。
また、「自分の今の生活」は仕事とプライベートの両方を指します。
自分が病気になると言った自分のリスクだけではなく、家族のリスクもあわせて想定しましょう。
また、最後に自分の感じている保険のイメージについてまとめておくといいでしょう。
例えば、掛け捨てはもったいなく感じるとか、今の保険料も高い気がするなど。
自分が今の保険に感じていることをまとめておくと、いざ保険を検討するときに役立つでしょう。
許容できるリスク
現在の自分の環境やリスクについて把握ができれば、あとはそのリスクに見合う保険を選択するだけです。
ここでポイントにしたいのが、許容できるリスクと保険でカバーすべきリスクは何なのか線引きをするということ。
まずは、「許容できるリスク」について考えていきます。
起こりうるリスクのなかで自己資金や公的保障等で乗り切れるリスクは、「許容できるリスク」でしょう。
こうした許容できるリスクには、必要以上に保険に加入することはありません。
これまでご説明してきた公的保障の内容を把握せずに公的保障と重複する保険をかけていたら過剰な保障となります。
保障されるときには手厚くて安心かもしれません。ですが、それが毎日の生活の逼迫に繋がってしまったら保険の意味がないのです。
保険でカバーすべきリスク
一方、保険加入すべきリスクとはどんなものがあるでしょうか?
- 自分が就業できなくなると収入面で生活が維持できなくなる場合
- 先ほどリスクのリストアップ時に挙げた例のように、収入面で問題はなくても、育児や介護で外注費が発生する可能性がある場合
- 医療費などが多くかかる場合
などが考えられます。
こうした場合を考慮し、公的保障で得られる金額を差し引いて必要な金額を算出。
最も当てはまる保険を選択することでリスクヘッジが可能です。
就業不能保険とは?
これまで公的な保障制度や個人事業主がこれからも働くうえでのリスク、保険の検討についてみてきました。
個人事業主が一番恐れるべきリスクは「働けなくなること」であると言えるでしょう。
会社員などであれば当面働けなくても金銭的に保障してくれる制度が社会保険上に組み込まれていますが個人事業主にはそれがありません。
個人事業主が「働けなくなる」事態は、現行の公的保障下では即収入減(またはゼロ)を意味します。
どのように保障を考えていくかはとても大切なポイントです。
ここでその「働けなくなる」という事態に備えられる保険として「就業不能保険」をご紹介します。
就業不能保険は、「被保険者が傷害または疾病により入院や自宅療養と言った、所定の就業不能状態になったときに一定額の給付金を支払う」というもの。
このような保険を出している保険会社も少なく、また、加入にあたっては収入の下限があることもあります。
自分がもし何かあったときにすぐ家族が困るという事態にならないように、こうした保険の加入も検討してみるといいでしょう。
個人事業主のリスクに見合う保険を
個人事業主の保険加入についてご紹介してきました。
個人事業主は自分が働けなくなる場合のリスクが会社員より高くなりがちです。
残された家族や働けなくなった自分がいざというときに困ることのないよう、リスクを棚卸しして適切な保険加入をしたいものです。
そのためには正しい公的保障の理解と、定期的な自分と家族の状況把握が不可欠です。
今回ご紹介した就業不能保険は、これまで個人事業主には公的な保険でほぼ保証されていない働けなくなったリスクに対して支給される保険です。合わせて検討してみてください。

マウスなどで行う操作をキーボードの操作のみでおこなう、ショートカット。PCの作業を大幅に効率化することができます。今回はWindowsの作業効率が上がる使用頻度が高く、すぐ覚えられるWindowsのショートカットを厳選して20個を紹介します!
Ctrlキーを使ったWindowsショートカット12選
まずはバリエーションの多いCtrlキーを使用したショートカットをご紹介します。
①Ctrl+Nキー
Word・Excelなどのソフトを開けている時に、新規作成します。
②Ctrl+Cキー
選択部分のコピー
③Ctrl+Xキー
選択部分の切り取り
④Ctrl+Vキー
選択部分のペースト(貼り付け)
⑤Ctrl+Zキー
前の動作に戻る
例えばある文書を推敲していて、文の書き換えをしたもののやはり前の文章に戻したい、と思ったときにこのショートカットを使えば元に戻せます。
押した分だけ動作が元に戻るので推敲が多い方にかなり便利です。
⑥Ctrl+Yキー
やり直し(元に戻した動作を戻す)
推敲して前の文章に戻したけど、やっぱり新しく作った方がいいと思ったときにこのキーを使えば新しい文章に再度戻してくれます。
⑦Ctrl+Shift+Sキー
名前をつけて保存
既存のExcelをベースに新しい資料を作っているときにうっかり上書き保存してしまい青ざめる経験をしたことはありませんか?
そういったことを回避するにはまず最初にこのショートカットをしてしまう習慣をつけるのもお勧めです。
⑧Ctrl+Sキー
上書き保存
Shiftキーを押さないと上書き保存になります。名前をつけて保存と間違えないようにしましょう。
⑨Ctrl+Aキー
シートやドキュメントの内容を全選択
⑩Ctrl+Pキー
印刷に移行
⑪Ctrl+Bキー
選択部分を太字にします。
太字や斜線などもショートカットキーで対応可能です。斜線は+Iキー、下線は+Uキーです。
⑫Ctrl+Esc
スタートメニューを開く
スタートメニューを開きたいときは、Ctrl+Escで開くことができます。パソコンによってはWindowsキーがついているものもあります。
Windowsキーのみを押すだけでもスタートメニューは開きます。
その他の役立つWindowsのショートカット8選
次に、Ctrl+以外の使用頻度の高いショートカットキーを8つご紹介していきます。
①Shift+Delete
ゴミ箱に入れずに選択したドキュメントを直接削除
完全にデータが消えてしまうので誤って消さないように注意しましょう。
②Alt+Enter
選択したアイテムのプロパティを表示
上記以外では、エクセルを編集している際に
エクセルのセル内で改行したいときに使うショートカットキーでもあります。
③Alt+F
ツールバーのファイルが開く
開くとその後の保存などのメニューもショートカットキーで案内してくれます。(Excel2016など)
④PrtScキー
スクリーンショット(画面の画像保存)
⑤Alt+←キー
前のウインドウに戻る
例えばインターネットを見ているときに、前のページに戻りたいときは
このショートカットキーを使うと戻ることができます。
戻ったページの後に閲覧したページに移りたいときはAlt+→で移ることができます。
⑥F5キー
作業中のウインドウを最新の状態に更新する
⑦Alt+Tab
開いているアプリを切り替える
複数のウインドウやアプリを開いて作業をする人が多いかと思いますが、
マウスを使わずに作業アプリを切り替える時に便利なショートカットキーです。
⑧Esc
今行っている作業の中止
エラーが出た時などに行うことが多いキーです。
Windowsで使用できるショートカットを20個ご紹介しました。今回ご紹介したものは、実際に使ってみて初めて作業効率が上がります。初めは慣れないことで時間が余計にかかるかも知れませんがキーを何回も使うことで覚えていきます。ショートカットキーを使いこなせるようになるとあなたの作業効率アップに必ず貢献してくれるでしょう。期日を決めて集中的に覚えるといいですね。ぜひ挑戦してみてください。

ショートカットキーは日々の作業効率を上げるための強い味方です。Windowsのショートカットキーについては書籍も多く出ていますが、Macについてはご存知ですか?特に、WindowsからMacへパソコンを買い換えた際は、ショートカットに慣れるまでに苦労している人も多いようです。
今回は作業効率を上げるために絶対覚えておきたい、Macのショートカットキーを紹介。特に使用頻度の高いショートカット20選をピックアップしています!
Command(⌘)キーを使ったMacショートカット20選
MacのCommand(⌘)キーはWindowsのCtrlキーに当たります。
ですがMacのCommand(⌘)キーは、WindowsのCtrlキーよりも登場頻度が高く、
ここを中心に覚えていくことで基本的なショートカットを網羅出来ます。
そこで今回はCommand(⌘)キーを使ったショートカットキーを20個ご紹介していきます。
① ⌘+N
新しいファイルの作成 or 新しいウインドウを開く
② ⌘+O
選択したファイルを開く
③ ⌘+C
選択した部分のコピー
④ ⌘+X
選択した部分のカット(切り取り)
⑤ ⌘+V
コピーまたはカットしたものをペースト(貼り付け)
⑥ ⌘+Z
一つ前の動作に戻す
例えばある文書を推敲していて、文の書き換えをしたもののやはり前の文章に戻したい、と思ったときにこのショートカットを使えば元に戻せます。押した分だけ、前の動作に戻すことができます。
⑦⌘+Shift+Z
やり直し(元に戻した動作を再度戻す)
上記の例の場合、推敲して前の文章に戻した後、再度新しく作った方へ戻す際に使用できます。
⑧ ⌘+F
ファイル内の項目の検索、または検索ウインドウを開く
⑨ ⌘+A
すべて選択
⑩ ⌘+P
操作しているファイルを印刷
⑪ ⌘+B
選択した部分を太字にする。
同じく斜体にしたいときは⌘+I、下線を引くときは⌘+Uとなります。
⑫ ⌘+W
最前面のファイルを閉じる
今最前面になっているファイルは⌘+W、全てのAppやファイルを閉じたいときは⌘+option+Wを押します。
⑬ ⌘+tab
Appの切り替え
開いているAppを、最近開いた順番に切り替えていくショートカットキーです。
⑭ ⌘+shift + チルダ (~)
ウインドウの切り替え
最前面のAppウインドウから、その直前まで使っていた順番にウインドウ切り替えを行います。
⑮ ⌘+S
フォルダやファイルを保存
⑯ ⌘+Q
Appの終了
⑰ ⌘+option+ esc
選択したAppの強制終了
最前面のAppのみを強制終了させるには、⌘+shift+option+escを3秒間押し続けます。
⑱ ⌘+shift+3
その画面全体のスクリーンショットを行います。
一部分のみのスクリーンショットを行いたいときは⌘+shift+4を押し、ポインターが十字になったところで該当箇所をドラッグします。
⑲ ⌘+H
最前面のAppウインドウを非表示します。
最前面以外の全てのウインドウを非表示にするときは、⌘+option+Hを押します。
⑳ ⌘+control+電源ボタン
Macを強制的に再起動します。
全てのAppを終了(保存していないファイル等があれば保存についてのメッセージがでます)し、再起動するにはcontrol+⌘+メディア取り出しキーを押します。
Macで使用できるショートカットを20個ご紹介しました。今回は特に使用頻度の高いCommandキーに絞ってご紹介してきましたが、ショートカットキーは実際に使ってみて初めて作業効率が上がります。初めは慣れないことで時間が余計にかかるかも知れませんがキーを何回も使うことで覚えていきますので、意識的にショートカットを増やしながら作業効率UPを図っていきましょう。

CARRY MEを通して「パラレルキャリア」という新しい生き方を知った2017年。これまで、仕事とは、ひとつの会社に属して行うものだと思っていた私に、多様性や新しい世界の可能性を感じさせてくれた年でした。この年には、ソフトバンクなどのような大手有名企業が副業解禁を発表したニュースもあったことからも、ひとつの会社に縛られない働き方へ流れのうねりを感じました。 11月には、厚生労働省が政府が規則改訂を行い、副業や兼業を事実上認めていくことを有識者検討会にて公表しました。 そして2018年。その流れから、副業や兼業について、これまで以上に強く興味を持つ人が増え、副業やパラレルキャリアの本格化が加速する年となりそうです。 そんななか、元メーカー勤務、現起業家兼ライターが、どのようにいかにキャリアチェンジを考え、現在のようなパラレルキャリアスタイルを得るチャレンジをしてきたかご紹介します。
女性ならではの葛藤。外資系メーカーを退職、そして妊娠。
8年間外資系メーカーに勤務し、後半の数年はセールスリーダーを担当していました。その間に結婚し、子供を持ちたいと思うようになっていましたが、その時には、もう30代前半。仕事で日々忙しくしているなか、子供ができるか不安でした。母親が不妊症で、私を生むまでに非常に苦労をしていたことを聞いていたので、とくにその不安は大きいものでした。また、その当時は仕事中心の生活でしたので、もし子供を持てたとしても、子育てをする生活へどのようにシフトしていけばよいのか、イメージをすることができませんでした。次第に、そのような気持ちを抱えながら仕事を続けるすることに対して、周囲への責任を感じるようになり、最終的に仕事を辞める決断にいたりました。仕事を辞めたことで、「子供ができるかわからない不安」「もし子供ができたときに仕事と子育てを両立できるかわからない不安」両方の不安を解消することができました。日本は、子供ができたとき、または子供を持つために仕事を辞めてしまう女性の割合が大変多いですが、かく言う私もその一人なのでした。
猛烈に働いたはずがまた働きたいと思うように
幸いにも、仕事を辞めて数ヶ月後に妊娠し、子供を持つことができました。3年後にも2人目の子供に恵まれ、子供を持ちたいという夢を叶えることができたのです。働いていた頃の私には想像のつかない子育て中心の生活が始まりました。
特に、第一子の子育ては、わからないことだらけ。第二子が生まれたばかりのころは第一子の赤ちゃんがえりもあり、本当に大変でした。今思い出そうとしても、記憶もあまりありません。
私は東京都在住なのですが、私の周囲のママ友達をみても、また区の統計を調べてみても、平成25年度のデータではありますが、第一子を出産する平均年齢が33歳前後。周囲のママたちも、ある程度仕事をしてきた人達が多く、これ以上仕事はしなくてもいい、というくらいまで仕事を全うしてから、子供をもったという人もとても多いのです。私も第一子の長男が、2〜3歳くらいになるまでは、そう思っていました。かなり猛烈に働いたと思っていたので、もう仕事はしばらくしなくてもいい、幸い夫が働いてくれているし、私は主婦として、お母さんの仕事を頑張っていこう。と思っていたのです。しかし、次男が生まれて1年くらいたったころ、また仕事ができたらいいな、と思うようになっていました。仕事をやめて4年がたっていました。
私はファッションやアクセサリー、おしゃれが好きです。お母さんになっても、もう少しファッションをもっと楽しみたい。それならば、いっそ仕事にすればいいのではないか。そう考えるようになりました。子供は二人とも男の子ですので、仕事をしていたときのようなハイヒールにシルク素材のニットにジャケットというわけにはいきません。ネックレスをしてもひっぱられて切れてしまいそう、、 いつしか私は洗濯のしやすい服とフラットシューズやスニーカーばかり履くようになっていました。フラットシューズやスニーカーにもおしゃれなものはたくさんあるにはありますが、もっと自由におしゃれを楽しみたい!と切実に思うようになっていました。
以前勤務していた会社はメーカーでしたがファッション関係ではなかったので、ファッションは未経験分野でした。洋服を作ったりすることは経験値不足で難しいけれど、取引先にはアパレルの企業も多くあったことから、一緒に何かお仕事をしたいと考えました。幸いにも、近所にアクセサリーメーカーを発見。自分でアクセサリーをデザインし、その会社に外注で製作を依頼して商品化することができました。ホームページは以前おつきあいのあったデザイナーさんに制作をお願いし、以前おつきあいのあったセレクトショップへに営業に伺い、ご縁があって良いスタートを切ることができました。
発作のように突き進めたアクセサリーブランドの起業ですが、思いのほか順調に動き始めました。
子育てをしながらの起業

起業して大変だったことは、子育てをしながら仕事の時間を捻出することです。例えば、ホームページを作る時に、まだ幼稚園にはいっていなかった次男の寝かしつけを終わらせてから毎日深夜3時4時まで仕事をして睡眠時間を削りました。昼は子供を公園につれていったり、子供優先の生活をしていたので、仕事をする時間がどうしても子供が寝た後になってしまいます。
営業に行くときには、長男が幼稚園に言っている間に次男を一時保育に預けて、なんとか綱渡り的に仕事をまわしていました。印象に残っていることは、次男が怪我をして病院にいっているときに取引先様から電話をいただき、泣く息子をあやしつつ電話応対をせざるを得なかったことです。電話の後直接商談に伺った際に、「お子さん泣いてましたね〜」という話になりました。しかしご担当者様が女性で、起業している私のことを応援してくださっていたので、温かく受け止めて下さり有り難かったです。
また、私の起業に夫が協力的だったことはとても助かりました。わたしたち夫婦はともにお互いのやりたいことを尊重し、応援するようにしています。ホームページ用の商品撮影の時に自宅をスタジオ代わりにし、2人の子供の世話を夫にお願いしましたが、サポート役をすすんで行ってくれたことは今でも忘れません。
パラレルキャリアへの挑戦
アクセサリーブランドの運営をしてきた過程で、運営を続けていく一方、アクセサリーブランドの運営のように在庫を持たなくてもできる仕事を平行して行い、複数の収入源を確保できないかという考えを持つようになりました。
そんなとき、コンサルタントの友人がFacebookでいいね!をしていたCARRY MEが目に入り、アドバイザーの毛利さんと面談させていただく機会をいただいたのです。そこで初めて「パラレルキャリア」という新しい働き方に出会いました。
これまで一つの会社に所属し、その仕事のことだけをするのが当然と思っていたので、自分のスキルを活かせる仕事を、平行して複数持つという考え方に新鮮さを覚えました。自分に仕事や会社をあわせるのではなく、仕事を自分にあわせる=マッチさせることもできるという新しい働き方に共感し、自分自身も実践してみたいと思うようになったのです。
パラレルキャリアのメリット
現在私には幼稚園に通う子供がいます。幼稚園は降園時間や午前保育の日が一定していないことから、固定の曜日に出社することが難しい状況です。仕事に使える時間は少ないけれど、仕事や世の中につながり、何か表現したい性分の私。毛利さんとの面談で、現在自分が使える時間や状況について詳しく話しを聞いていただき、CARRY ME の運営しているオウンドメディア、本音採用他のメディアのライターの仕事を紹介していただきました。リモートワークが可能なライター業務は、自宅で自分のペースで行える仕事のため、仕事に使える時間に限りがある生活を送りながらも新しいキャリアをスタートすることができました。他にも、簡単な画像の作成なども行えるので、そのスキルを使って新しい仕事も頂いています。
幼稚園ママという、時間に制約が多い生活を送りながらも、自分なりに少しずつ、キャリアアップができていることに満足しています。私と同じように、仕事時は限られるけれども仕事をしたいと考える人にとって、パラレルキャリアは、とても有意義な働き方であると感じています。
個人で起業していると、周りと取引やコミュニケーションを積極的にとらないと、意外と孤独なことに気づきます。そんなとき、CARRY MEとつながりを持てたことで仕事上のネットワークが増え、仕事自体に幅が広がりができたこともうれしいです。
次男が幼稚園を卒園して、小学校に入学したら、本格的に仕事時間を増やしていきたいと考えています。CARRY MEや本音採用などオウンドメディアライターの仕事を通じて、これまでの自分が知り得なかった仕事への新しい考え方や、必要なスキルを知り、学ぶことができるようになってきたことにやりがいを感じています。その意識を大切にし、自分に必要なスキルをさらに学びながら、自分の運営しているアクセサリーブランドにもそのスキルのシナジーを反映させて、あたらしいことにも挑戦し続けていきたいです。

個人事業主・フリーランスのためのスケジュール管理
フリーランスや個人事業主としてで仕事をしているみなさんは、スケジュール管理はどのようにされていますか?従来どおりの手帳の方もいれば、最近はオンラインスやアプリで管理されている方も多いでしょう。
ここではフリーランス・個人事業主の方に役立つ、スケジュール管理方法についてご紹介していきます。フリーランス・個人事業主という形態で仕事をする上での大きなメリットは、「自分で自由に時間を管理できる」というところにあります。しかし、その分、自己の管理能力が求められます。納期まで時間があるからと、仕事をせずにいても、文句を言ってくる上司もいません。自分が仕事をするプレーヤー兼管理者として、自分自身をしっかり律することが重要です。
一方で、時間を自由に使えるからと、予定をきつくつめこみすぎて、オーバーワークになりがちな側面も見逃せません。子育て中の場合は、さらに育児・家事の時間配分も必要になります。 スケジュール管理能力が、フリーランスの仕事の成功を制す鍵といっても過言ではないでしょう。
スケジュールを決める前に、時間の使い方と必要な環境について確認しよう
スケジュールをたてる前に、行うべき仕事にどのような時間の使い方が必要なのか、どんな環境が必要なのかを検討して確認しましょう。
・お礼状やお礼のメールを書く:パソコンや手紙を持っていれば、隙間時間でも行うことができます。
・納品書、請求書を発行する:印刷が必要な場合、プリンタのある場所で仕事を行わなければなりません。
・打ち合わせや商談:先方の都合と照らし合わせてスケジュールをたてなければなりません。
・原稿を書く、予算をたてる、プレゼンを作成:集中して作業をすることが必要な場合、なるべく邪魔の入らない場所で、まとまった時間を確保する必要があります。
上記のようにタイプの異なる仕事は手当たり次第行っていくよりも、似た仕事で分類し、まとめて行うことで効率的に仕事をすすめることができます。それぞれの仕事の時間配分、重要度を確認して、優先順位の高い仕事から行っていくことができればベストでしょう。
スケジュール管理のコツ① 集中して行う仕事にふさわしい時間帯とスケジュール
たとえば、誰もまだ起きてこない早朝は、クリエイティブな仕事や重要な仕事を行うのにふさわしい時間だといえます。伊藤忠ファッションシステム株式会社取締役であり、日経ビジネスオンラインや読売新聞で連載を持つジャーナリストの川島蓉子さんも、 “1年365日、毎朝、午前3時起床で原稿を書く暮らしを20年来続けている。”といいます。
参考 URL http://ifs-miraiken.jp
しかし、朝がどうしても弱い方もいらっしゃると思います。その場合、一人で集中して重要な仕事を行うには、深夜が一番捗るという場合もあるので、自分の持っている性質と、仕事内容、スケジュールをよく吟味してスケジュールを組みましょう。
スケジュール管理のコツ② 隙間時間でできる仕事を準備しておこう
隙間時間とは、どのような時間でしょうか?たとえば銀行や郵便局で順番を待っている時間、通勤時間中、電車に揺られているとき、子供の習い事の送迎で子供の帰りを待っているとき、などなど注意深く認識するようにしてみれば、たくさん見つけることができます。その時間に、何かタスクをすますことができれば時間を有意義に使うことができます。隙間時間でできる仕事を確認して、準備しておき、その時間がでてきそうな時には必要なものを持っていきましょう。待ち時間のイライラを、タスク完了時間に変えることができれば、一石二鳥です。
スケジュール管理のコツ③ グーグルカレンダーやアウトルックなど、オンラインによるスケジュール管理
スマートフォンのアプリやグループメンバーでシェア可能なスケジューリングアプリケーションで、スケジュール管理を行う方法もおすすめです。グループで仕事をする場合、お互いのスケジュールを共有して確認できる点もメリットです。しかし、オンラインでないと確認できない、そして一目で、この一週間、自分やまわりがどれだけ忙しく仕事量があるのかが、ぱっと一目で判断がつきづらいというデメリットがあります。
スケジュール管理のコツ④ 紙の手帳の利便性
ライター個人の体験で恐縮ですが、フランス製バーチカル手帳の元祖、クオバディスに以前勤務していた経験もあることから、私は長年手帳を使ってスケジュール管理を行っています。愛用の手帳は、見開き一週間で、時間軸があるバーチカルタイプを使っています。使っているベージの端を切り取ることができ、今使っているベージをぱっと開けるさりげない工夫にも愛着を感じます。左ページが時間軸のページ、右側にはノートページで構成されているエグゼクティブノートというタイプを使っています。英語表記のようですが、日本語版です。

(参考URL http://www.shop.quovadis.co.jp/SHOP/1653.html)
時間軸部分には、スケジュールを時間軸にそって記入し、右ページにはTodoを印して、タスクが終わったらチェックをつけます。Todoにやり残しがあれば、次週に持ち越して、また新しい週のノートページに書くTodoに追加記入します。この手帳にある時間軸は8時から22時です。会社勤めの時はなんとか足りていたこの時間軸、個人事業主、フリーランスとして仕事を始めてからは、子供が寝静まった早朝や深夜に仕事をすることがよくあるので、本当は24時間軸の手帳が自分にはふさわしいのかも、と思ってしまうのですが、愛用している手帳の、正方形という形が好きなので、どうしてもこれを毎年購入してしまいます。
(24時間軸のバーチカル手帳もあります。商品名 H24/24 フランス語版 日本祝日シール対応 参考URL http://www.shop.quovadis.co.jp/SHOP/1001000047.html )
アナログな手帳のよさは、やはりスケジュールがぱっと目に入ってくる視認性に優れる点だと思っています。きちんと時間軸にそってスケジュールを記入してみれば、どのような行動をすべきなのか、その行動をするためには、どのような時間の使い方をすべきなのかが自然にわかるのです。
忙しい時ほど、重要性や緊急性について冷静に考え、仕事をどのようにふりわけてスケジュールをたてられるのか分析することが重要です。本来ならば、緊急で重要から仕事を行っていき、その後にも、重要度の高い仕事からタスクを完了すべきであるのでしょうが、フリーランスや個人事業主は、使える時間や環境が一日の中で変化することが多いです。そのなかで、仕事に対する優先順位のつけかたが重要になってくると考えられるので、自分らしい考え方、仕事のすすめかたを考え、仕事に追われすぎずにタスクをこなし、生産性を高めていくことができるようにしていきましょう。

あなたがキャリアチェンジを考える時は、どんな時ですか?
これまで安定だとみられていた企業が経営危機に陥ったり、働き方改革が2017年の流行語大賞にノミネートされるなど、戦後の働き方に対する常識やロールモデルが崩れようとしています。
とはいえ、キャリアチェンジやパラレルキャリア、副業、転職など仕事について変化の伴う決断には勇気や判断力のいるものです。どんな人が、どんな理由でキャリアチェンジをしたのかはあなたのキャリアを考える上でも参考になるかもしれません。
実は私は、安定した職と言われる公務員を辞め、今パラレルキャリアへのキャリアチェンジにチャレンジしています。今回は私の体験談から、パラレルキャリアやキャリアチェンジについての理解の一助になればと思います。
なぜ私は公務員からキャリアチェンジしたのか?
私は結婚を機に転居し、公務員へ転職をしました。夫の仕事先である転居先は双方の実家からも遠く、家庭と両立しながら実家の援助を受けずに仕事を続けられる職業として選択しました。
2年弱ほど市役所職員の仕事をし、第一子の産休・育休を取得。キャリアチェンジのタイミングはこの育休中に訪れました。家庭の事情で夫の実家の近くへの転居を検討することになり、夫が転職することになったのです。市役所職員はその市役所でしか原則的には勤務できません。育休中に私はこうして公務員を辞めることになりました。
そのまま主婦として生活することもできたのでしょうが、私は仕事をしていることで社会とのかかわりを感じられるタイプで毎日の育児にノイローゼ気味でもあったので、仕事をしたほうが絶対に子供と私のためになると直感していました。
転居後すぐに1歳の第一子の息子を保育園へ通わすために保活。保活の目途がたった所で転職活動を本格化。結婚前にしていた仕事から、マーケティングや営業、事務などの仕事を正社員で探しました。しかし、子連れの転職はなかなかうまくいきません。この時私は30歳。
年齢的にも決してどんな職種にもチャレンジできる年齢ではないんだなと、感じました。結局私は結婚前に勤務していた会社にアルバイトとして復職することになりました。理由は、息子の保育園申請時に「求職中」で申請をしたので、入園後3か月以内に就業をしなくてはならないという規定があったためでした。
子育て中のキャリアチェンジの壁

こうして結婚前の会社にアルバイトとして復職した私ですが、どうして転職活動がうまくいかなかったのでしょうか。振り返ってみると、以下のような要因があったと思います。
①そもそも、転職活動中に子供がいることを積極的に伝える必要があったのか?
この点は後にCARRYMEアドバイザーの方との面談時にご指摘いただいたのですが、子供がいると積極的に伝えすぎると、特に正社員求人だと仕事に対してマイナスな印象を受け取られる可能性が上がるように思われます。
「お子さんがいるということよりも、その仕事で自分が何をしたいのか、どんな熱意を持っているのか、何を相手方(企業)に提供できるのかを伝えることが大切で、お子さんがいるという話はその次でもいいはずです。」というお話を頂き、腹落ちしたのをよく覚えています。
例えば書類には積極的に記載せず、面接時にさらっという程度でもよかったのかもしれません。現に私は書類さえ通らない状況がずっと続きました。子供の病気での欠勤などで仕事に穴をあけられることなどを企業側も恐れてのことでしょうが、結局は「子供か、仕事かという2択」のような状況が日本ではまだ残っていると感じました。
また私自身、子供がいることに囚われすぎて、子供がいるということを戦略的に情報出ししていくべきところその意識が欠けていた(素直に伝えすぎた)と気づかされました。
②子供が小さく、かつ子供がいながらの仕事について経験がなかったことで、明確な対策を面接時に明言できなかった。
やっと面接にこぎつけた会社でも、子供がいながらの仕事について経験がなかったので子供が風邪をひいたときなどの対応について明言ができなかったことが転職活動の敗因の一つだと分析しています。
子供が病気になったときの対策については病児保育等も事前に調べていたものの、調べただけの知識で不安感が面接時ににじみ出ていたのかもしれません。例えばすでにママとして仕事をしている友人などに相談するなどしてそうした不安を取り除いてから面接に臨むべきだったと反省しました。
パラレルキャリアへのキャリアチェンジ
私は今、結婚前の会社にアルバイトとして週4回働きながら、「本音採用」ライターやWeb関係の会社でライティングやアプリ運用のお仕事を週1回させていただく、パラレルキャリアへキャリアチェンジをしました。その理由は大きく分けて2つありました。
①現在の職場の金銭面・待遇面での問題
結婚前の職場にアルバイトとして復職した私ですが、社員の時の年収と時給アルバイト・ボーナスなしという今の年収、業務内容を比較した時、使い物にならなかった新卒1年目の自分よりはるかに年収が低いことに愕然としてしまったのです。
時給なので当たり前と言えば当たり前なのです。しかし、業務内容としては新卒1年目の自分より役に立っているはずだという自負もありましたし、定時までいられない・子供の病気などでたまに休むという条件が入るだけでこんなに給与として評価されないのかという思いが強くなりました。
また、息子は定期的に小児科に連れて行かなくてはならない事情もあり、週5日、私が家から1時間かかる会社へ通っているために小児科に連れて行くのが毎週週末になってしまいます。息子本人に負担をかけたり週末に遊びに連れていく時間が減っていることも、「このままではいけない」と私の背中を押した一因でした。
②60代になっても自分の力で働き続けたいという私の目標
私の目標は、「60代になっても働いていられる仕事やスキルを身に付けること」「そのために自立していけるほどの収入をきちんと稼ぎ続けること」でした。
これからは、企業の定年はどんどん後ろ倒しになる一方でいつ会社が傾くか先の読めない時代です。また、私も今現在の主収入がアルバイトなので、一生やっていくと決められる仕事やスキルを身に付ける必要があると痛感していました。ゆくゆくは、自分の名前だけで食べていかれる(=フリーランス)状態になることが一番いいのではないかとぼんやり考えるようになりました。
こうした思いを抱えながら、第二子の産休・育休中の昨年夏ごろ、FacebookでshAIRの広告を経由してCARRYMEを知りました。私のような経歴の人間でもご紹介いただける案件はあるのか不安を抱きつつも、まずはご相談依頼のメールを差し上げたところ、すぐにお返事をいただきアドバイザーの方とお話させていただく機会を得ました。
正直、私の経歴ではとても「プロ」と言える経歴ではないことは自覚がありましたのでどんな怖い方が担当してくださるのだろうと思っていました…
実際にお会いしたアドバイザーの毛利さんは、ふんわりとした笑顔が印象的な物腰もとても柔らかい方でした。また私の話を親身になって聞いてくださり、ママ先輩としてどんなことを気にしながらキャリアチェンジをしていくべきか大変的確なアドバイスをいくつも頂きました。プロとして信頼できるアドバイザーさんだと感じています。
そして今、週1回在宅・業務委託でさせていただいているお仕事をご紹介いただきました。在宅での仕事が1日できたことで、子供も業務終了後に小児科に連れていくことが可能となり、非常に助かっています。また、このキャリアチェンジのおかげで少しづつではありますが私なりのキャリアを形成し始めたところです。「私なりのキャリア」、私が今目標にしていることや今回のキャリアチェンジで大切にしたことについて次にお話ししたいと思います。
私の今後のキャリアチェンジ

私が今回のキャリアチェンジで大切にしたことは、毛利さんからのアドバイスの一つでもある「本当に自分のやりたかったことを仕事にする」ということです。
そこで立ち止まって自分は何がしたかったのか、小さい頃から遡って考えました。見えてきた「私のしたいこと」は「文章を書くこと」でした。そこで、Webライティングができるお仕事をご紹介いただき、半年ほど仕事をしています。半年ほどWebのお仕事をさせていただいて、まだまだ勉強中ではありますが
自分の作成した記事が目に留まる機会があったり、お仕事しているクライアント様の利益に貢献できるのは非常にうれしいです。
一方で、私はキャリアチェンジについてもう一つ大切にしていることがあります。それは「家族、特に子供との生活」です。夫は一般企業で正社員として働く会社員ですので、残業もありますし、私がいわゆる「ワンオペ育児」で子供たちと向き合う日もあります。
まずは家族が楽しく安心して日々を過ごせる基盤を作る。そのうえで自分のやりたいことを諦めない。正社員の転職では実現できなかった「家庭と自分のやりたいこととの両立」をするためパラレルキャリアを選択した今は、逆に時間や場所の制約が少しなくなり、自由になったと感じています。
公務員として働いていた時より、時間も場所も、仕事内容も、自分の意志で自由にできることは大きなメリットを感じます。
副業が禁止されている公務員ではできなかった仕事ができている、それも自分がやってみたかった仕事。これは、公務員が嫌になって辞めたわけではなかっただけに
思わぬ副産物を得てラッキーだったという思いがあります。
これからも、子供の成長や家族の変化、自分の目標とのバランスを考えながらキャリアチェンジを続けていきたいと思っています。
今回は私のキャリアチェンジを通じて、パラレルキャリアやキャリアチェンジについてご紹介してきました。CARRYMEに出会うまで、私の中には正社員としての転職以外は自分にとって損になるのではないかと感じていました。しかしパラレルキャリアを選択することで私自身、少しの仕事環境の変化で大きなメリットをいくつも得ることができました。また、パラレルキャリアは子供がいても自分のしたいこと・できることを表現すれば道が開けていく、柔軟な選択肢でもあると感じています。もし今仕事、働き方などにもやもやとした思いを抱えているのなら、まず一歩踏み出してみませんか?

銀座のレンタルオフィスおすすめ5選!
ブランド力の高い銀座。地下鉄で銀座線、有楽町線、日比谷線の乗り入れがあり、JRの有楽町も近く、日本有数の企業や、官庁などへのアクセスも大変便利です。一流のモノに触れることができる環境で、刺激を受けながら仕事ができる点も大きな魅力のひとつでしょう。
日本一の地価を誇る銀座では、一般的なオフィスを借りると毎月高額な費用が必要となりますが、レンタルオフィスであれば、低コストで、最高の環境を手にすることが可能です。ここで紹介するレンタルオフィスを参考に、銀座での新しい働きかたを探ってみましょう!
おすすめの銀座レンタルオフィス 銀座アントレサロン

アントレのレンタルオフィスは、銀座で5つの拠点を持ち、すべてのオフィスは最寄り駅から5分以内と利便性も◎。プランによっては、他のエリア(東京、新宿、池袋、横浜等)のオフィスをを利用可能。スタッフが常駐しており、急な来客があっても対応してもらうことができる。運営しているアントレは、起業についてのセミナーや交流会などを多く開催しており、コミュニティを広げたい方にもおすすめ。
| 場所 | 東京都中央区銀座7丁目13番5号 NREG銀座ビル1階 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階 アクセス:東京メトロ日比谷線、都営浅草線 「東銀座駅」徒歩2分 東京メトロ銀座線「銀座駅」徒歩5分 JR線、東京メトロ銀座線、都営浅草線「新橋駅」徒歩6分 東京都中央区築地4丁目1番1号 東劇ビル8階 |
|---|---|
| 料金 | 【初期費用】無料 【月額料金】個室プラン:50,000円 フリーデスクプラン:9,505円 バーチャルオフィスプラン:3,800円+その他オプションサービス(専用TEL・FAX番号やコピー&プリンタ等) |
| おすすめのサービス | インターネット・電源、ロッカー利用、専用電話番号提供、専用FAX番号提供、電話秘書、郵便物転送、法人登記、複合機、FAX、お茶だしサービス、社名掲出、無料オープンラウンジ、商談スペース、セミナールーム等 |
おすすめの銀座レンタルオフィス リージャス銀座三丁目

リージャスが運営するハイグレードな銀座のレンタルオフィス。受付はバイリンガルで、海外との取引を行っているユーザーにもおすすめ。外資系オフィスプロバイダー企業のリージャスが運営しているため、リージャスのメンバーシッププログラムのビジネスワールドに加入すると、世界3,000拠点、国内100拠点以上のリージャスビジネスラウンジが利用でき、フリードリンク、フリーWiFi、リージャスの貸会議室とテレビ会議の割引のサービスが受けられる、世界中で仕事を行うノマドワーカーは要チェックのオフィス。
| 場所 | 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館 5F アクセス:東京メトロ銀座線/丸の内線/日比谷線「銀座駅」より徒歩4分 JR/東京メトロ有楽町線「有楽町駅」より徒歩5分 |
|---|---|
| 料金 | 【初期費用】直接お問い合わせください 【月額料金】 個室レンタルオフィス:203,900円~ 半個室(セミプライベートオフィス):83,900円~ バーチャルオフィス:15,900円~ |
| おすすめのサービス | 入居者専用無料会議室(コミュニティミーティングルーム)、 インターネット (Wi-Fi) 、受付サービス(バイリンガル)、オフィス家具、ビジネスラウンジ、カフェテリア、裁断機。大型ホチキス、シュレッダー、郵便・宅配受付、電話取り次ぎサービス 等 |
おすすめの銀座レンタルオフィス PORTAL POINT YURAKUCHO

有楽町駅直結利便性の高いオフィスビルに所在。 築49年のヴィンテージビルをリノベーションし、広さとおしゃれさを兼ね備えたなエクステリアとインテリアが魅力的。 大小のワークプレイスと、共有スペースを有効に利用できる。人気のオフィスのため、入居待ちが多いが、おしゃれなリノベーションオフィスで仕事をすることに重要性をおくユーザーには特にお勧めできるオフィス。
| 場所 | 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11階 アクセス:東京メトロ有楽町線「有楽町駅」 D2出口直結 JR山手線「有楽町駅」より徒歩1分 東京メトロ日比谷線「日比谷駅」B1出口より徒歩1分 |
|---|---|
| 料金 | 【初期費用】直接お問い合わせください 【月額料金】 レンタルオフィス 約24坪〜41坪 満室 スモールオフィス 3名利用 195,000円 シェアオフィス 30,000~ 100,000円(フリーデスク、ブース利用など) |
| おすすめのサービス | ビジネスサポートサービス、コンシェルジュデスク、コミュニティラウンジ、ルフレッシュルーム、会議室、複合機、WIFI, 郵便ボックス、ライブラリー、ロッカー(大中小)荷物預かり等 |
おすすめの銀座レンタルオフィス Bizcube

ホテルライクなデザインが魅力的。ミーテイングスペースはソファ、オフィスは快適なチェアなど、家具にもこだわりを提供。受付電話を常時対応可能。信用アップにつながるサービスを提供。ビルに入居会社名を表示してもらえ、視認性と信用アップにも。
| 場所 | 東京都中央区銀座5-6-12 みゆきビル(受付7F) アクセス:東京メトロ銀座線/丸の内線/日比谷線「銀座駅」より徒歩4分 JR/東京メトロ有楽町線「有楽町駅」より徒歩5分 |
|---|---|
| 料金 | 【初期費用】入会金108,000円他 詳細は直接お問い合わせください 【月額料金】 現在空室4〜6人用オフィス 216,000円 1〜2人用から5〜7人オフィスまであり(現在入居中) |
| おすすめのサービス | 受付電話秘書、常駐秘書、ファックス転送、フリーテスク利用、カフェエリア利用、法人登記・住所利用、郵便・宅配物転送、ロッカー、防音性能、会議室、SECOM入退室セキュリティ、定期清掃、備品販売、接客対応、ドリンクサービス 等 |
おすすめの銀座レンタルオフィス ベンチャーデスク銀座

コストをおさえることを重視し、起業家への満足度を追求。入居時に支払う保証金は退去時に返金。好立地で便利、会議室を大小兼ね備え、利用目的にあわせた使用が可能。ドリンクサービスも。毎日毎西清掃がはいり、大変清潔な環境。起業家むけ相談窓口を設置し、きめ細かなサービスを行う。
| 場所 | 東京都中央区銀座6-16-12 丸高ビル3F アクセス:東京メトロ銀座線/丸ノ内線/日比谷線 「銀座駅」A3出口より徒歩5分 都営浅草線/日比谷線「東銀座駅」4番出口より徒歩2分 |
|---|---|
| 料金 | 【初期費用】保証金 50,000円~ プランにより変動 詳細は直接お問い合わせください 【月額料金】 フリーデスク 25,000円 スタンダードデスク 40,000円 エグゼクティブデスク 60,000円 グループデスク 90000円 バーチャルデスク 10,000円 現在空室4〜6人用オフィス 216,000円 1〜2人用から5〜7人オフィスまであり(現在入居中) |
| おすすめのサービス | 電話番号利用、転送サービス、郵便物転送、複合機、スキャニング、会議室利用、秘書サービス、ロッカー、プロジェクター、登記利用 |
銀座は敷居が高いと思っているあなたも、レンタルオフィスであれば低コストで便利さや働きやすさを満喫できるでしょう。 それぞれのオフィスに魅力的な特長や利便性があります。あなたがオフィスに求めるニーズをみたしてくれるレンタルオフィスを見つけたら、ぜひ利用してみてくださいね!
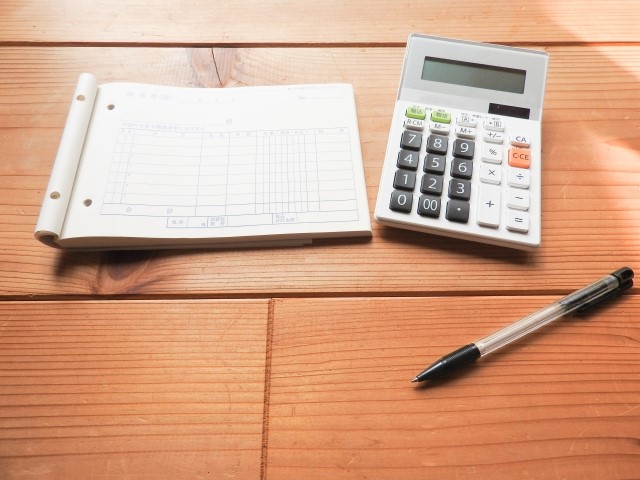
請求書の作成を簡単に行うには?
フリーランスや個人事業主になると取引先との間で必須になるのが請求書の作成です。
しかしフリーランスやパラレルキャリアをスタートさせたばかりで請求書を作ったこともない、作る方法もわからないという方もいるでしょう。筆者も最近までその一人でした。
そこで今回は請求書を簡単に作成する方法と題して、
請求書の必須記載事項や簡単に作成できる無料ツールのご紹介をしていきます!
請求書の作成に必要な記載事項
まずは、請求書の必須記載事項を確認しましょう。これについては、国税庁HPに請求書作成時に必要な記載事項が5点明示されています。
①書類作成者の氏名又は名称
請求書を作成する(≒請求する)人が誰なのか、は必須事項です。
②取引年月日
月締めで請求書を作成する場合は、〇月分ご請求書とタイトルに記載すると先方もわかりやすいですね。
③取引内容
「業務委託費」「○○作成料」など、どんな契約内容なのか記載しましょう。
④取引金額(税込み)
契約書を締結した際、単価が税込みか税抜きかを確認し、税込み請求額になるよう記載しましょう。
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
請求先ですね。確実に記載が必要です。その際、会社名で請求書を作成する場合は「御中」、個人名で請求書を作成する場合は「様」とあて先にも注意しましょう。
国税庁HPには上記の通りですが、それ以外にも下記内容も記載するとお取引先様にスムーズに処理をしてもらうことができます。
①請求者の住所・電話番号
不明点があったとき、お取引先様から問い合わせがしやすいよう、連絡先の記載を行うと良いでしょう。
②請求発行日、支払期限
発行日や支払い期限があるとお取引先様の処理期日がわかりやすくなります。
また、支払い期限は契約時に設定しているようならその期日を記載します。
特に設定がないようなら、まずはお取引先様と相談の上決定しましょう。
おすすめの請求書作成ツール4選

請求書に必要な記載事項について説明してきましたが、こうした請求書の必須記載事項を網羅して自分でエクセルなどで請求書を作成するのは非常に手間がかかります。
そこでおすすめの方法が、簡単に請求書を作成できる「請求書作成ツール」を使用することです。オンラインサービスで使いやすいものばかりなので、請求書作成初心者でも、いつでもどこでも簡単に作成することができます。無料で請求書が作成できるツールもあるのでぜひ参考にしてみてください。
おすすめの請求書作成ツール1:misoca
misocaの特徴
・請求書作成から郵送・メール送信までが数分でできる簡単な操作性
・会計ソフト「弥生」と連携可能
・自動作成機能で作成効率化
「たった3ステップ、1分で請求書を作成」と謳っているmisocaは、
簡単な請求書作成手順が魅力。郵送(有料プラン)にも対応可能です。
テンプレートも多彩で、自分の気に入ったデザインを選ぶことができます。
毎月請求書を作成する場合、請求書を指定日に自動作成する設定も可能。
忙しくて請求書作成を忘れてしまうという方にも安心です。
料金プラン(税抜、カッコ内は請求書作成可能数)
無料プラン:あり(10通まで/月)
プラン15:月額800円 年額8,000円(15通まで/月、追加は1通70円、郵送は1通160円)
プラン100:月額3,000円 年額30,000円(100通まで/月、追加は1通70円、郵送は1通160円)
プラン1000:月額10,000円 年額100,000円(1,000通まで/月、郵送は1通160円)
おすすめの請求書作成ツール2:freee
freeeの特徴
・請求書・見積書・納品書を何通発行しても無料
・会計ソフトとの連携で申告まで対応可能
・銀行口座などとの連携で会計処理も自動化
freeeは、請求書を無制限で無料発行できるサービスを提供。機能は書類発行・電子保存などがメインでシンプルですが、会計ソフトと連携することで入金ステータスの管理や経費計算、確定申告の書類作成などの機能を追加することができます。会計ソフトは銀行口座やクレジットカードとの連携機能、スマホ撮影での領収書取り込み機能などもあり、使い勝手の良さが特徴です。メールのサポート体制は無料プランから利用できます。
料金プラン(税抜)
無料プラン:あり
(freee会計を契約した場合)
スターター:月額1,480円 年額11,760円
スタンダード:月額2,680円 年額23,760円
プレミアム:年額39,800円(月額なし)
おすすめの請求書作成ツール3:MFクラウド
MFクラウドの特徴
・複数人の利用にも便利な権限機能と作業履歴
・印影やロゴを登録して請求書に印字可能
・請求書の自動作成機能
MFクラウドはスタートアップして複数人で会計処理をする際にも安心な機能として
閲覧だけ・編集だけができるスタッフを登録できる権限機能があります。
また、自分の屋号にあわせてロゴを持っている方にはうれしいロゴを請求書に印字できるサービスも。
会計ソフトとの連携も可能で、会計業務の効率化も図れます。
料金プラン(税抜)
無料プラン:あり
パーソナルミニ:月額800円 年額9,600円
パーソナル:月額1,280円 年額11,760円
パーソナルプラス: 年額2,980円 月額なし
おすすめの請求書作成ツール4:board
boardの特徴
・書類を案件ごとに管理 見積書を作ると自動で納品書や請求書など他のテンプレートも作成
・通知機能付きで業務漏れを防止
・見積もり資料から売り上げ状況を予測
実際の業務・経営を行っている経営者自身が開発しているので
業務目線での使いやすさが最大のメリット。
書類のデザインの良さや請求書作成の簡単さという部分もさることながら、
見積書から売り上げ見込みを予測できたり
売上目標・損益分岐点・粗利目標を事前に入力しておくことで予算管理も可能。
請求書処理という作業面でも、経営面でもフリーランスの強い味方になりうるツールです。
料金プラン(税込)
無料プラン:なし(各有料プランを30日無料でお試し可能)
パーソナル:月額980円
ベーシック:月額1,980円
スタンダード:月額3,980円
プレミアム:月額5,980円
請求書を簡単に作成する方法についてご紹介してきました。今回ご紹介した以外にも簡単に請求書が作成できるクラウドサービスがあります。フリーランスにとって請求書の作成や会計の管理も自分の収入に直結するので非常に重要ですが、簡単に済ませたいところでもあります。あなたの今の業務内容に応じて、フィットするクラウドサービスを見つけていきましょう。

個人事業主は「経費」を適切に処理して節税を!
個人事業主やフリーランスで仕事をするにあたって、「経費」は必ずチェックしなくてはならないポイントです。
給与所得者は、「給与所得控除」という形で収入に応じて決められています。それ以上経費がかかった場合も、上限を超えて控除することができません。(参考:国税庁HP 給与所得控除)
一方、個人事業主であれば、「経費」項目を適切に処理さえすれば、控除金額の上限は定められおらず、結果的に大きな節税につながります。
年明けには確定申告も迫っているので、ここで個人事業主が「経費」として申請できる代表的なものをご紹介します。ぜひ、今年の確定申告にお役立てください!
そもそも、個人事業主の「経費」とは何か?
個人事業主になったら「経費」をしっかり把握しよう、などと経費のことは話題に上るものの、
そもそも個人事業主の経費はどのようなものを指すのでしょうか?申告先であり、調査をしている国税庁のホームページでは、次のように説明されています。
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
簡単に言えば、「事業を行う上でかかった経費」ということになります。
ただし事業を行うと言っても、個人事業主はプライベートと仕事の境目があいまいになることもしばしばです。
その点について同じく国税庁ホームページでは次のように説明が加えられています。
個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
つまり、プライベートでの使用分と事業分との経費を分けて、事業分のみを申告してくださいということになります。
事業所得を決定する際の「経費」の考え方として
①申告する年(1月1日~12月31日)の事業を行うにあたってかかった経費であること
②プライベートと事業分は分けたうえで、事業分の費用のみを経費として計上すること
の2点が絶対に守らなくてはならない大きなポイントとなります。
これを無視して、事業収入と経費のバランスが明らかにとれていない申告になっていると、税務調査の対象になることも考えられます。ルールを守って、事業所得の経費を計上しましょう!
個人事業主の「経費」代表例7選!
では実際に個人事業主が「経費」として計上できる代表例を7つ取り上げます。
1. 通信費
対象例:電話代、携帯料金、プロバイダ料金、書類の郵送費、切手代
注意点・コメント
プライベートと仕事で同じ携帯やプロバイダを使用している場合は、先述の通り事業で使用した分のみ、経費として計上することができます。事業按分(事業で使用した費用の割合)を決める場合には、使用時間を目安にすると良いでしょう。仕事とプライベートでちょうど同じ程度使用していて、月額1万円かかっている場合は、事業按分50%で「5千円」を経費として計上することができます。
2.旅費交通費
対象例:電車・バス・新幹線等の公共交通機関の代金、宿泊費用
注意点・コメント
打ち合わせや取材・営業など、事業を行う上で交通機関を使用したり宿泊した際の費用を経費として計上します。
例えば、取材のついでに延泊して友人に会った場合、取材に行くまでの往復交通機関は経費計上できますが、宿泊費は(取材のみであれば宿泊しなくても帰ってこられる場合)経費計上はできません。また、電車やバスでは領収書をもらうのが難しいと思いますので、
出金伝票にメモをするなどして対応しましょう。
3.消耗品費
対象例:文房具、事務用品、名刺
注意点・コメント
金額として10万円未満、耐用年数1年未満のものを事業で使用した際に計上する費用です。似たような勘定科目に「雑費」がありますが、雑費は少額で使用頻度の低く、消耗品ではないものとされ、基本的には使わない勘定科目という認識でいるといいと思います。雑費は引っ越し費用やごみ処理費用、証明書の手数料などに使われることが多いです。
4.減価償却費
対象例:車、家具、家電(高額なもの)…耐用年数表に記載のあるもの
注意点・コメント
個人事業主でもパソコンやカメラ等の高額な仕事道具を購入したり、事業によっては家具や車などをそろえることもあるでしょう。そのような、「高額で長期間使用するもの」を購入した時に何年かかけて経費を按分して計上する経費が減価償却費です。
「何年かかけて」というのは、「法定耐用年数」が国税庁で公表されており、それに基づいて各項目ごとに計算し処理していくためです。また、取得価格が10万円以上20万円未満の場合は「一括償却資産」として3年間、同じ金額を按分することで計上するという方法もあります。
5.租税公課
対象例:個人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税
注意点・コメント
固定資産税や自動車税などは、事業で使用している分のみ按分して経費計上が可能です。また、所得税や個人住民税、相続税等は、事業ではなく個人にかかる税になるので計上してはいけません。
国民健康保険は事業経費にはできませんが、「社会保険料控除」という別項目で控除対象として申告可能です。
6.水道光熱費
対象例:電気代、ガス代、水道料金
注意点・コメント
自宅が事務所となっている場合、按分が非常に難しい項目ではあります。電気代の場合、自宅にいて電気がついていた時間から事業をしていた時間分だけを按分して計上可能なようですがガスや水道はそれが認められないケースも多々あるようです。ガス代や水道料金を経費に計上したい場合は所管税務署または税理士に相談してみると良いでしょう。
7.接待交際費
対象例:取引先との食事代、取引先へのお中元・お歳暮代、手土産、慶弔費
注意点・コメント
取引先との打ち合わせを兼ねた食事などに使用する経費項目ですが、自分の事業規模に対してあまりにも接待費が大きいなどの不自然な点があれば税務調査の対象となります。
あくまでも常識の範囲内で申告することが大切です。
また、慶弔費など領収書のでないものについては、交通費の時と同じく出金伝票などで処理すると良いでしょう。
個人事業主が申告時に役立つであろう経費7選をご紹介してきました。経費はどんなに細かいものでも出金台帳や領収書の管理を徹底し処理を行うことで、きちんと節税ができます。年明けには申告シーズンです。申告前に慌てないようきちんと整理をして、適切な経費計上を行い、賢く節税をしましょう!

![CARRY ME [キャリーミー] |個人のプロに仕事が舞い込むサイト](https://carryme.jp/magazine/wp-content/themes/carryme/common/images/cta_bt01.png)