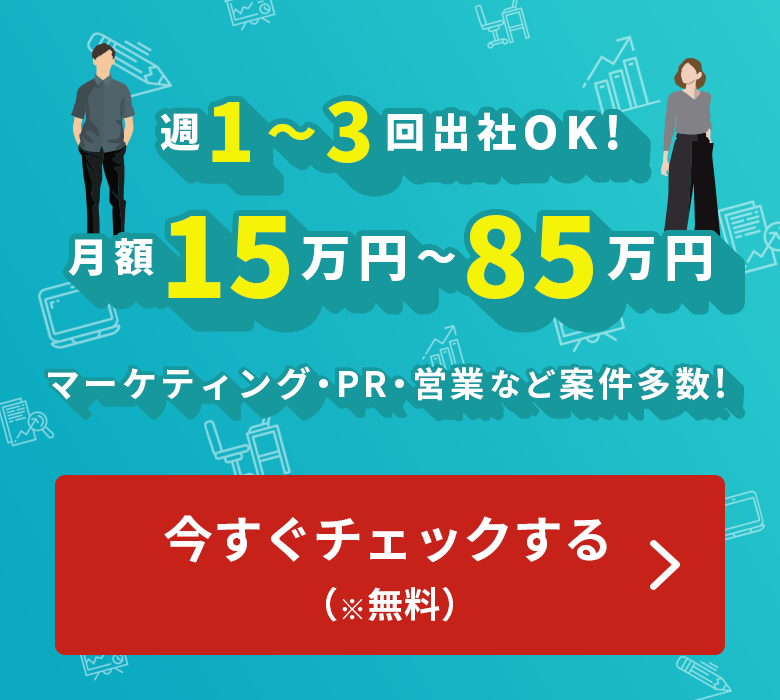投稿者: NODAshu

『実践版 成功するB向けオウンドメディアを作る!』と題して、コンテンツマーケティング手法について取り上げる、今回はその第2回です。
第2回めの今回は、20年もの前にあのビル・ゲイツが発していた言葉を皮切りに「コンテンツ」と呼ばれるものの深淵に迫っていきたいと思います。
前回に重ねて、音楽の話題も盛ってしまいました。ぼくが非常に音楽好き(主に、ハードロック)でもありますので、しばらくはそんな話題にもお付き合いください。では、今回もよろしくお願いします。
もはや良質なコンテンツでなければ戦えない
ひところ、Content is king と言い方が広がったことを記憶されている方はどれくらいいるでしょうか? コンテンツマーケティングという言葉が広がる以前、コンテンツSEOという方法が跋扈する頃にあちこちで語られましたが、この言葉は実はビル・ゲイツが1996年に語っていた言葉でもあります。
その後、インターネットの主役を他社に譲ることになりますが、PC分野での王者として先の先を予言した言葉として、現在もある意味「伝説」化しています。
一部、引用しましょう。
50年前に始まったテレビ革命は、テレビメーカーを含む、様々な業界に波及していったものの、長期的な成功を手中に収めたのは、メディアを使って、情報や娯楽を提供した人達であった。
インターネット等のインタラクティブなネットワークにおいては、「コンテンツ」の定義は広範に渡る。例えば、コンピュータソフトウェアもコンテンツの形式の一つであり — 非常に重要度は高い。事実、今後もMicrosoftは、このタイプのコンテンツを最も重要視していくだろう。
雑誌をそのまま電子の領域に移動するだけでは、オンラインで成功を収めることはできない。オンラインメディアの欠点を克服するだけの深さ、そして、インタラクティビティ(双方向的な要素)が、印刷メディアのコンテンツには欠けているためだ。
インターネットは、専門的な科学の情報を交換する仕組みに革命をもたらしている。印刷版の科学雑誌は、発行数が少なく、そのため、価格が高くなる傾向がある。大学の図書館は、科学雑誌の顧客の大半を占めている。専門的なオーディエンスに対して情報を配信するこの手法は、ぎこちなく、ペースが遅く、また、高額のコストがかかるものの、代案が存在しない状態であった。
パブリッシャーは、大勢のオーディエンスを集めるために、小額の料金を請求する煩わしさから開放されるだろう。
成功を収める者は、アイデア、経験、そして、製品の市場、つまりコンテンツの市場として、インターネットを進歩させていく。
翻訳文は、http://www.seojapan.com/blog/content-is-king-by-bill-gates
による
(1996年3月1日 ビル・ゲイツ)
1996年に語られた言葉とは思えないところが、さすがビジョナリーとしてのビル・ゲイツです。まさに、圧巻です。
現在は、既に2018年。ビル・ゲイツが思い浮かべた未来は実現しているのでしょうか?
少なくとも、多くの人がある興味からスマホに話しかけ、あるいは検索キーワードを入力し、特定のページを表示させ自身の課題解決を図るという世界は実現しています。
だからこそ、その結果に「責任」を負うのが情報発信者たるメディア側であることは論を待ちません。
そのメディアの「定義」は明確か?
さて、話をコンテンツマーケティングに進めましょう。
先に上げた言葉を言い換えて、Content is Magic という言葉を掲げました。
「優良顧客を生み出すものが良いコンテンツだということ」というのが、その言葉が示す意味。
コンテンツマーケティングとは、見込み客や顧客にとって価値のあるコンテンツ(=良質なコンテンツ)を提供し続けることで、興味・関心を惹き、理解してもらい、結果として売上げにつなげるマーケティング戦略のこと。何度も訪問して購入してくれるリピート(=優良)顧客を育てるということは、つまり、継続的に訪問したくなるコンテンツづくりをするということです。
では、ユーザーを惹きつける継続的かつ長期的なコンテンツづくりとは、どのように行なえばよいのでしょうか。
考えるのは、「誰が喜んでくれるだろう?」という視点です。
先の検索をするというユーザーの行動を思い出してください。
改めて「良いコンテンツ」を考え直す
検索キーワードの絞り出し方や、その検索キーワードに対応したコンテンツづくりについては、また改めて実践的な方法をお伝えしていこうと考えていますが、今回はまだその前提となるコンテンツの考え方について深掘りをしたいと考えました。
繰り返しますが、「誰が喜んでくれるだろう?」と考えることこそが一番有益であり大切だと考えられるからです。
「求められる音楽」と「天才が作る音楽」
ここで、前回に引き続きコンテンツとしての音楽を取り上げてコンテンツの制作を深掘りしていきたいと思います。
音楽家で天才という代名詞で多くの人が思い浮かべるのは、クラシックの世界ならモーツァルトになるのではないでしょうか。モーツァルトがその天才性にも関わらず短い生涯を閉じ、しかも誰の遺体ともわからぬまま共同墓穴に埋葬されたというのは実に悲しい逸話です(映画『アマデウス』でも胸の痛くなるシーンでした)。同様に天才という言葉で語られながらも、難聴を抱えていたなどのサイドストーリーから大きな人気を博しているのがベートーヴェンです。特に、日本では年末の「第9」は欠かせない風物詩でもあります。この二人の音楽家に共通するのは、それまでの貴族とのパトロン契約から開放されて自由な職業音楽家として生きようとしていたという点に尽きます。
そして、この当時、音楽を消費するということは現在で言うライブを体感することと楽譜を購入することに他なりませんでした。余談ですが、ぼくはギターはもちろん大好きですが(何しろハードロック好きですから)、ピアノ曲もかなり好きでベートーヴェンのピアノソナタは聴き込んでいます。現在私たちが目にするピアノという楽器はベートーヴェンが優秀なピアノ職人とともに作り上げたものだというのも豆知識です。特に、ベートーヴェンは、ペダルを効果的に使う奏者だったそうです。
それは天才が生み出す音楽の数々でした。
時代は(場所も)進み、ぼくが若者だった時代の音楽の世界の英雄が先ほど「引退」を宣言しました。小室哲哉氏です。引退の顛末はここでは語りませんが、時に彼も「天才」と呼ばれていました。80年代、彼が敏腕プロデューサーとして数多くのヒット曲を世に送り出し大活躍をしていた時代に語っていた言葉があります。
正確に引用ができないので、こういうことを言っていたという程度に読んでいただきたいのですが、
「ヒット曲には幾つもの方程式がある。歌手(アーティスト)に合わせて、またそのテーマ(歌詞)に合わせてそのパズルを埋めていくだけだ」というような話でした。
音楽的には、
・Aパターン:カノン進行 |C|G|Am|Em|F|C|F|G|
・Bパターン:(王道)|FM7|G7|Em7|Am|
・Cパターン:(小室) |Am|F|G|C|
など、ポップスの分野では定番化したコード進行があり、Cは小室哲哉氏が多用していたパターンです。(『Get Wild』がこのパターン)。
また、せっかくなので、少し曲を生み出すというところに焦点を当てて語ると、ぼくの大好きなThe WHOによくあるパターンですが、ギターで音楽を作るという考え方で、そのままギターを横にスライドさせて転調させるという方法(有名な例が、『SummerTime Blues』です)。似たような例は、坂本龍一氏の『Behind The Mask』でもあります。これは、ギターで演奏するのに非常にかっこいい曲ですが(クラプトンのカヴァーが有名ですね!)、ギターで作る曲を無理やりピアノで作ろうとした曲だと本人が語っています。
音楽の話題はこれくらいしして、まとめましょう。
「良いコンテンツ」を生み出すために必要なこと
- その情報を受け取る側に立って、必要なものごとを組み立てる
これは、まさにあらゆる曲を量産していた小室哲哉氏が実践していた方法でもあります。よく知られた逸話で、歌詞を書く際には女子高生の会話を書き溜めたノートから印象的な言葉をピックアップしていたなどというものもあります。 「軸をずらす」ことで良質なコンテンツを誕生させる
誰もが知っている事柄をちょっと横から見直して新しい発見をする。いわゆる「バズ」るためのテクニックでも語られますが、軸をずらすということを意識することはとても有効です。先の音楽の例でいうと、『SummerTime Blues』や坂本龍一氏の『Behind the Mask』が良い例です。計測を踏まえたPDCA(コンテンツの修正)
実は、一番肝心なのはこの3つ目です。記事を書いたらおしまい、公開したらジ・エンドではありません。ある指標を持って計測を踏まえ、繰り返し記事をアップデートしていくことこそ最善の答えです。
まとめに代えて
今回は、「良いコンテンツ」に関して、約20年前のビル・ゲイツの予言めいたコラムの言葉からコンテンツの魔法を考察してみました。
余談ですが、筆者は10年前には電子書籍事業に真剣に取り組んでいまして、音楽と書籍の融合を「電子書籍」で実現したいと本気で考えていました。無残に夢と終わりましたが、「電子書籍」それ以前に制作されたCD-ROMというメディアをもう既に誰も覚えていないのかもしれませんが、ほとんどが(現在のスタンダードな)パソコンではもう確認することもできないものばかりです。幾つか、まさに魔法のような傑作も存在していますので、もしご興味があれば古いマシンを用意してぜひ見てみてください。
クリエイティビティを大いに刺激されるはずです。
さて、次回は「ターゲットとゴール」の設定について、少し具体的にぼくが携わってきたメディアの事例も参考にしながら紐解いていきたいと思います。お楽しみに。
企業・採用担当者の
みなさまへ
CARRY MEでは、年収600-1000万円レベルのプロ人材を
「正社員採用よりもコストを圧倒的に抑えながら」
「必要な時に、必要なボリュームで(出社もOK!)」
「最短1週間の採用期間で」
ご紹介いたします。

その一環で今回から『実践版 成功するB向けオウンドメディアを作る!』と題して数回にわたって、コンテンツマーケティング手法について取り上げていきたいと思います。
そもそも、「コンテンツマーケティング」とはどういう取り組みを示す言葉でしょうか? その定義から進めていきましょう。
この「コンテンツマーケティング」が多くの企業で注目を集めたきっかけは、やはりPPC広告の単価が上がってきたため広告の費用対効果が合わなくなってきたという理由が大きかったように思います。もっと単純に、広告効果が落ちてきたためと言ってもいいかもしれません。
その前に「オウンドメディアってなんですか?」という問いかけもありそうです。詳しくは次回にしっかり定義づけから解説したいと思いますが、まずは、簡単に「企業や組織自らが発行する広報誌やパンフレット、Webサイトやブログなど、自らが所有し消費者に向けて発信する媒体のこと」というざっくり理解を前提としましょう。
第一回めの今回は、ちょっと変化球ですが、数年前に話題になったベストセラーを題材に、コンテンツマーケティングを振り返ってみます。ぼくが非常に音楽好き(主に、ハードロック)でもありますので、そんな話題からスタートさせてください。楽しく読み進められて、課題となっているものごとの理解が深まる、そんなコンテンツを目指します。
ベストセラー『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』からコンテンツのPRを学ぶ
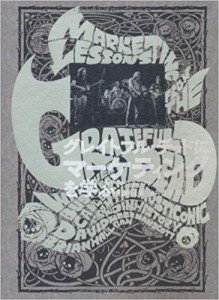 2017年華々しく上場した「ほぼ日」。代表の糸井重里氏が積極的に関わったのが、『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』という書籍です。日本では2011年に翻訳出版されました。
2017年華々しく上場した「ほぼ日」。代表の糸井重里氏が積極的に関わったのが、『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』という書籍です。日本では2011年に翻訳出版されました。
https://www.1101.com/unusual2/
「フリーミアムモデル」「ソーシャルメディア拡散」などの現代的なマーケティング手法を、40年も前からやっていたというのです。
まず、この書籍で紹介されているポイントを列挙しましょう。
コンテンツを無料で提供するということ
グレイトフル・デッドは、観客によるライブの録音を奨励していました。ライブを録音するファンは「テーパー」と呼ばれ、彼らがなるべく高い音質で録音できるよう専用の場所がミキシング・コンソールの後ろに設置されていたそうです。Napster(覚えている人はいますか?)もYoutubeもなかった時代のことですよ。
シェアを奨励するということ
念のために追加で説明をしますが、録音メディアはカセットテープです。デジタルデータではありませんので、要注意。コピーをするたびに音質は劣化してしまう時代のお話ということでもあります。このテープをコピーしたり共有したり編集して創作したりすることを、グレイトフル・デッドは許してくれました。録音を販売しない、が唯一の条件。
バンド側がそれを開放したことで、その音楽はファンによって広がりやすくなり、それがさらなるファンを生むという好循環ができたのです。
(念のために、20歳を越えた娘の周りにも確認したら、誰一人カセットテープを知りませんでした)
個性的であれ、ということ
 グレイトフル・デッドは、自分たちが変わり者であるという自覚をしていましたし、そのようにアピールしました。コアなファンにも風変わりであることを奨励し、クリエイティブな表現を後押ししてくれました。言葉を少し変えると、「ユニーク」であれ、というメッセージにつながっています。そして、コアなファンとは「手紙」などのやりとりをしていたそうです。チケットの販売が決まれば、真っ先にファンに知らせる。ファンの忠誠心は強くならざるを得ません。結果的に、それは強固な仕組みとなりました。
グレイトフル・デッドは、自分たちが変わり者であるという自覚をしていましたし、そのようにアピールしました。コアなファンにも風変わりであることを奨励し、クリエイティブな表現を後押ししてくれました。言葉を少し変えると、「ユニーク」であれ、というメッセージにつながっています。そして、コアなファンとは「手紙」などのやりとりをしていたそうです。チケットの販売が決まれば、真っ先にファンに知らせる。ファンの忠誠心は強くならざるを得ません。結果的に、それは強固な仕組みとなりました。
トライ・アンド・エラーに躊躇しないということ
グレイトフル・デッドのライブは、すべて即興による演奏スタイルで講演内容はそれぞれまったく異なるものになりました。リーダーのジェリー・ガルシアによると、ライブの80%は即興で、ほかのバンドのように同じ曲を同じように演奏するスタイルに近いものは、20%とのこと。出来が良い日もあれば、悪い日もある。だからといって、自分たちのスタイルを変えることはしない。その頑なさが、また新しいファンを導きました。
行商人コミュニティともシェイクハンドするということ
あまたあるロックバンドは、オフィシャルグッズを確実に売るために、自分たちの管理外の業者は排除しています。我々が見知っている光景は、あくまでそのような管理下でのグッズ販売。しかし、グレイトフル・デッドのライブ会場内では、デッドが手を組んだ行商人コミュニティメンバーが独自に(言わば、勝手に)作るグッズを販売しました。デッドは、ブランド管理をゆるくしてファンを取り込んだかと思いきや、行商人コミュニティとも手を組み自分たちの応援団を組織したのです。
代表的なキャラクターグッズに、デッドベアーがあります。日本でもちょっとしたブームになったことがありますし、現在も熱心なファンがいるようです。
では、「コンテンツマーケティング」として、取り上げられる方法を列挙してみよう
駆け足で『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』の紹介をしてきました。コンテンツにとって重要なのは、ファンが喜ぶものを無料で提供し、熱烈なファンを醸成し、彼らがさらにファンを拡大する行動をしてくれている、そのような仕組みができあがっていたということです。
では、ここで改めて「コンテンツマーケティング」で語られる方法や重要なポイントを列挙してみましょう。
ペルソナ設計をする=ターゲットを明確にすること
「ペルソナ」とは、マーケティング業界では「象徴的な利用者像」のこと。「ターゲットユーザーをより具体化した架空の人物」を作り上げることで、ターゲットの行動パターンやニーズをより明確にできます。一般的には、エクセル(スプレッドシート)やカード型ファイルで整理されることが多いようです。
この、ペルソナ設定によって、コンテンツマーケティングの方向性が決まります。
ペルソナを設計する際には、必ず実際のデータを利用することが重要です。例えば、実際のサービス・商品の販売状況から、現実の利用者・購入者の年齢層・性別が特定できるならば、それを活用するのが賢明。あるいは、アンケート等を行なってどのような属性の方々がユーザーとなっているのか、リサーチすることもよいでしょう。それに加えて市場調査データ等を加味しペルソナを設計していくという流れが基本になります。
ここで重要なのは、思い込みや推測のみで自社に都合の良い「ペルソナ」を作ってはいけないということです。
対策キーワードの選定あるいは、記事化するためのニーズを徹底リサーチすること
ターゲットが明確になったら、そのターゲットの抱えるニーズを徹底的にリサーチすることです。そこから記事にすべき要素が見つかります。
ターゲットユーザーがどのような人物なのかを把握できたならば、彼らがどのような問題を抱えていて、どのような情報を必要としているのか、ペルソナの行動パターンや趣味・嗜好から洗い出してみます。
さらに、そのニーズに沿ったキーワードを設定し、それに沿って作られたコンテンツであれば、結果的に検索ユーザーに見てもらえる確率が高くなり、それがまた Googleからの評価につながり検索結果に反映されていきます。
ターゲットニーズを探るための方法としては、
- ユーザーを集めた座談会を開く
- カスタマージャーニーマップを作成する
などさまざまな手法があります。これらについても、この連載で深掘りしていきましょう。
ユーザーの「なに」を解決できるか狙いを定めること
実際に記事を書き始めるのはここからです。
ここまでは、記事を書き始めるための準備作業でした。コンテンツマーケティングには、実際に記事を書く以前の「設計」が肝心です。
ぼくは、常に「お土産を渡せるコンテンツであるか」を何度も問いかけることだと説明しています。
記事を読んでもらったあとに、きちんと
「これは始めて知った、よかった〜」
「なるほど、いままで漠然としてたけどよく理解できた〜」
「これは、ユニークなことだ、面白い!」
などなど、読者自身がそれまでに体験し得なかった「お土産」を渡せるコンテンツであることが重要なのだと考えています。
そのことで、読者自身が課題解決を図ることができたり、何か次へのアクションの呼び水になったりすることができれば、その記事の価値が高いということが言えます。
そうした記事は、会社にとって大事な試算となります。
ソーシャルメディア上で拡散されやすいオリジナリティを
ソーシャルメディアは「コンテンツの拡散」を目的に活用します。グレイトフル・デッドにとっては、カセットテープがそのためのメディアでしたが、現代はソーシャル・ネットワークが複数あります。
コンテンツマーケティングにおける流入は、「検索エンジン」と「ソーシャルメディア」が主流です。ソーシャルメディアは、拡散されれば早い段階で新規ユーザーを獲得できる可能性がありますので、効果的に活用するための経験が必要です。いうまでもなく、拡散されるための記事はどういうものかという前提条件があります。
- 人に教えたくなるものである
- 役に立つ情報だから保存しておこうと思えるものである
アクセス解析=効果測定して、必要あれば記事を改修する
繰り返しますが、コンテンツマーケティングとは「ユーザー」=読者が起点となる施策なのですから、ユーザーの反応を無視したまま続けていては成功から遠のくばかりです。
具体的には、きちんとアナリティクスを進めて、記事の改修やメディアの見直しを繰り返していかなくてはなりません。
Googleアナリティクス、 Google Search Consoleなどの設定は、メディアの開始からすぐに済ませておくべきです。
一方、意外と注意の必要なのが「エゴサーチ」で、 Twitter上などで自社サービス名やホームページの URLなどを検索してみると、アンケートや座談会では得られないような率直な意見を確認できます。
この項目でもっとも重要なのは、コンテンツ(各記事)の評価です。
単純に PVが多いという単純な指標だけで判断をしていてはいけません。メディアがうまくいかないと悩まれる場合の原因の8割がこの評価が誤っているためによるものです。
この点についても、連載の中で充分に解説をしていきます。
これからのB向けコンテンツのあるべき姿を希求する試みを始めよう
コンテンツマーケティングを成功させるためには、 ペルソナを設計して ターゲットユーザーへの理解を深め、彼らがどのような情報を欲しているのかを洗い出し、そのニーズに沿ったキーワードの選定を行ない、「役に立つ」記事を作っていくことです。
さて、このたびはB向けメディアにとっての必要な方法は何か、と課題を少し絞っています。C向けとの違いはどこにあるのでしょう?
実は、本音採用もそうなのですが、ぼくが携わるメディアの多くは、デバイス別の比率が現在の一般的な数字とは大きく異なっています。80%がPCでの閲覧です。もちろん、レスポンシブ対応していたりスマホ用のサイト分岐をしていたり最適化もきちんとしていますが、ビジネス時間に会社であるいは会社のパソコンで閲覧するユーザーがほとんどになっています。
一番大きく異なるのは、この点ではないかと考えます。
キュレーション系のビジネスメディアも人気のようですが、それらはスマホアプリ化が進んでいます。スモールメディアでもスマホアプリを作る動きもありますが、悩みを抱えたビジネスマンがどこで見るか、どこで考えるか、そして次のアクションをどうするのかを考えたうえでのコンテンツ設計はとても重要だと考えるのです。
現在のあり方にしても、まだ完成されたものではありませんから、今後のあるべき姿を考えていく姿勢がまだまだ大切だと実感もしています。この連載を通して、その新たな道筋も明らかにできればと思います。そう考えると、今回取り上げたグレイトフル・デッドの40年も前からのチャレンジにもその大きなヒントが隠れているように感じられてなりません。
では、これからの連載にご期待ください。引き続きのご購読をよろしくお願いいたします。
企業・採用担当者の
みなさまへ
CARRY MEでは、年収600-1000万円レベルのプロ人材を
「正社員採用よりもコストを圧倒的に抑えながら」
「必要な時に、必要なボリュームで(出社もOK!)」
「最短1週間の採用期間で」
ご紹介いたします。

早いもので今年ももう終わりですね!
皆さんにとって、今年1年どんな年だったでしょうか。
忙しい日々に追われなかなか普段は振り返ることが少なかったりしますが、少し時間に余裕がある年末年始はゆっくりと自分と向き合うことができたりして、私自身は結構好きです。
温かいお茶を飲みながらゆったりとした気持ちで読んでいただきたい・・・
今回はそんな内容の記事です。
ちょっと「採用ライティング」とはズレますが、お付き合いいただければうれしいです。
お金をもらわなくてもしたいと思える仕事
突然ですが、皆さんは今のお仕事「お金をもらわなくてもしたい」でしょうか?
「はい」と答える方はそう多くないかと思います。
仕事は多くの方にとって生活の糧を得るためのもので、要はお金のために仕事をしている方がかなりの割合でいらっしゃることと思います。
それは、もちろん正しいことです。
プロである以上、労働や成果物に対して正当な対価を得ることはとても大切なこと。
「やりがい搾取」という言葉もありますが、自分の能力やキャリアをいたずらに安く売ることはあまりおすすめできません。
でも。
「事業内容」「仕事内容」「理念」「社風」「ともに働く仲間」に惚れ込み、たとえ報酬が少なくてもこの仕事をしたい! と思える仕事に出会えることは本当に幸せなことです。
逆もしかり。報酬が高くてもどうしても気が向かない仕事、会社というのも存在するでしょう。
この違いは一体なんでしょうか。
当事者意識とリスペクト
キャリアアドバイザーとして、毎日平均3~4名ほどの方とお会いしています。
CARRY MEの登録者の多くはフリーランスか自身で会社を経営している、もしくは正社員であったとしてもパラレルキャリアを目指している方(または実践している方)です。
接していて感じることは、皆さん本当にご自身の仕事を愛していらっしゃる、ということ。
だからこそ独立してフリーランスで仕事されていたりするのだと思いますが、「やらされている感」がない。「自ら選び取っている」という当事者意識が高いのです。
そのような方は当然のことながら総じて魅力的で、だからこそ多くの企業からのオファーが舞い込みます。
弊社の登録者様の中で次々とオファーを勝ち取っている美人広報ウーマンの方がいらっしゃるのですが、まさに「広報の仕事が好きでたまらない」といった感じの話しっぷりでした。幸せそうでした、本当に。
逆に、「やらされている感」があるうちは、どんな仕事であっても愛せないのではないかなと思います。他責的な言動も多くなるので、企業からのオファーも遠のきます。
会社も選ばれる立場
また、最近は法人担当もさせていただくので多くの企業様に訪問させていただいておりますが、担当者の方(多くは経営者)の様子、お話のされ方でその会社の社風、理念、成長性、採用における強さ弱さが見えてきます。
どんなに忙しくても、たとえ深夜まで仕事をしていても(事実、0時過ぎた後にメールのやり取りをすることもあります 笑)、楽しそうな方は本当に楽しそうですね。そのような会社はほぼ100%社員同士の仲がいい。お互いをリスペクトしている感じがあります。
そしてそのような会社は採用もうまくいっているのです。
面接の場で人事(もしくは経営者)が感じる以上に、候補者の方々はその会社の雰囲気を見ています。表情、言葉の端々、社員同士の会話、部下の方に対しての接し方・・・
どんなに取り繕っても敏感な方には伝わりますし、優秀な方ほど敏感です。
会社も選ばれる立場。会社自身の魅力を上げていかなければいけません。イコールそこで働く方々の魅力を。
まとめ
お仕事を探す個人の方も採用したいとお考えの法人様も、結局「いまの仕事が好きか、情熱を傾けられるものなのか」という部分が肝心なのではないかなと思います。
本当に好きなことであれば真心を持って取り組むことができるしそれが結果実績につながる、本当に自社を愛していればテクニックがあまりなくても率直な思いを表現するだけで、それが一番の採用広報になったりする。
CARRY MEを通じて求職や採用に成功されている個人・法人の皆様を見ていると本当にそう感じます。
そう感じられない仕事、そう感じられない会社であれば改革が必要かもしれません。
転職なのか、組織改革なのか、手法はさまざまだと思いますが、好きではないことを自分を偽りながら長く続けていくことは苦しいことです。
自分の仕事、自分の会社を愛し、「たとえお金をもらわなくてもこの仕事がしたい」といえる方を人材紹介の仕事を通じて増やしていくこと。
それが私の願いです。
そんな仕事を、CARRY MEを、私は心から愛しています。
今年1年本当にありがとうございました。来年また笑顔でお会いしましょう! よいお年を★
企業・採用担当者の
みなさまへ
CARRY MEでは、年収600-1000万円レベルのプロ人材を
「正社員採用よりもコストを圧倒的に抑えながら」
「必要な時に、必要なボリュームで(出社もOK!)」
「最短1週間の採用期間で」
ご紹介いたします。

実は、去年の誕生日前後は、とある事件があって、会社の財務状況はちょっと(かなり)ピンチだった・・・
(現在はCARRY MEという新規事業が軌道にのり、キャッシュフローも黒字でまわっているのでご安心ください。)
新規事業が順調に滑り出すまでの苦しい期間、何とか短期間でキャッシュを工面できたので、
「そこで気づいた2つの重要なスキル、法則」
についてみなさまのお役に立てれば、と思い、まとめてみた。
(キャッシュを簡単に稼ぐ方法、ではない。残念ながらそんな方法は、僕には思いつかないので・・・)
仕事を獲得するための2つのスキルとは?
誰しもピンチは1回や2回は経験するもの。
そんな時のためにも、また日常の収入を増やすためにも、個人として、会社として、受注額を増やせた2つのスキル・法則(特に2番目)は多くの方にご参考になるのではないかと思う。
キャッシュを工面した方法は、
単純に、個人としてまたは会社として、これまで蓄積してきたスキルを活かし「顧問業」で、1時間5万円から7.5万円で多くの法人に自身のスキルを切り売りさせて頂いたというもの。(現在も3社で継続中)
※顧問業は他社の仲介のものもあり、顧問仲介会社は受注額の50%を収入としているので、大澤が1時間7.5万円の収入を得るのであれば、企業は1時間15万円の報酬を支払っていることとなる。
大澤の場合は、これまで事業立ち上げを5回経験し2度売却、中堅企業(土屋鞄製造所)での取締役としてのEC事業等成長させた経験、コンサルティング会社(ドリームインキュベータ)でのコンサル経験などがあったので、
- 新規事業立ち上げ
- EC事業での課題発見、課題解決
この2分野で数多く依頼を頂けた。
フリーランスや起業家、営業マンには参考になるかもしれないので、仕事を獲得するための2つのスキルについて思ったことを整理してみた。2つとは、簡単にいうと、「提供するスキル」と「相手にちゃんと伝えるスキル」である。
「需要が多く供給が少ない分野」での、スキルを磨いておくことが重要
単純にスキルがある、ということが重要なのではなく、
「需要が多く供給が少ない分野」で一定以上のスキルがあることが重要である。
当たり前だが、需要が少ない分野で、供給が多い分野でスキルがあっても仕方がない。
需要はあるが供給が多い分野だと、特徴のないヨガインストラクター、どこにでもいるマナー講師、などは最たる例だろう。
では、どの分野のスキルが、需給のバランスからしてねらい目(つまり需要多く供給が少ない)のか。
それは、弊社でまとめているデータがあるので、10月にでも公表しよう。
僕の場合は、幸いなことに、「新規事業の立ち上げ」も、「EC」も、需要が非常に多く、一方供給者(経験者)が少なく、
- 沢山の企業から、
- 高めの単価で(高めの場合、1時間あたり15万円の支払い基準
仕事を頂くことができた。
(現在は手一杯で、残念ながらほとんどお断りさせて頂いています)
さて、重要なスキルの2番目である。
スキルはあるだけではダメで、
「きちんと相手に使える!と伝わらないと活用されない」、
という点から2番目のスキルが必要となる。
スキルの抽象化と具体化、その使い分けというスキル
これは、僕ができている、というよりも、現在のCARRY MEに登録しているプロ人材を見て気づき、僕も見習っているものだ。
以下の両者には明確な違いがあった。
「優秀で仕事を獲れているプロ人材」(プロ人材=業務委託契約をベースで働く、起業家やフリーランス、子育て中のキャリアウーマン等)
と、
「優秀かもしれないけど、仕事を獲れないプロ人材」
一言でいうと、
「自身のスキルの抽象化と具体化、それをうまく使い分けられるスキル」である。
順を追って説明しよう。
実際、CARRY MEのスゴ腕のプロ達は、他の個人より、こうして10倍もの受注額につなげている。
自身のスキルを抽象化するスキル
たとえば、Aさんにオウンドメディア構築、運用のスキルがある(と、Aさんは思っている)としよう。
Aさんは前職ではそれなりに結果を出せており、実績はあった。
しかし、そのスキルをB社に活かそうと、B社にスキルを提供して対価を得ようとした場合、
B社は、
「そのスキルって再現性あるの?たまたま前職で、運よく、もしくは周りのリソースを使って、結果が出たのではないの?」
と、少し穿って考える。
そうしたときに、自身のオウンドメディア構築・運用のスキルを「抽象化」できると、相手から本物のスキルとして認められやすいのだ。
例えば、以下のようにスキルを抽象化して説明したらどうだろう。
僕のオウンドメディア構築・運用のスキルは、ざっくり以下の5つに分けられます。
- 現実的かつ目的に沿った目標設定とそれまでの施策の設定
- SEOとSNS中心での施策実施
- 良いライターかどうかの区別、ライターを集めるスキル
- 編集スキル SEO対策含め、1日30記事程度は編集可能
- Google Analyticsを使ったPDCA活用スキル
単純に、オウンドメディア構築できます、こんな100万PVまで成長させた実績あります、のような一辺倒の営業トークというよりもよほど説得力があるだろう。
抽象化していくと、大体途中で質問がある。
「例えば、良いライターと悪いライターってどうやって見分けるの?」
とか。
そこでも、抽象化して説明しても良いし、ここで具体的な例を出して説明しても良い。
抽象化する主目的は、上記の通り、「このスキルはうちの会社でも使える!(再現性がある)」と思ってもらえることだ。
が、もう1つ、利点を挙げるとすると、「この人、頭が良い」と思ってもらえやすい(笑)。
外資系コンサル勤務の人など、(本当に頭が良い人も沢山いるが)、抽象化することがうまく、そのことも一要因あって頭が良いと思われやすい、という事実はあると思う。
ちなみに、メジャーリーガーのイチローさんは、ご自身を天才じゃないとの前提のもと、以下のコメントを残している。
「天才は、なぜヒットを打てたか説明できない。ぼくは、きちんと説明できる。だから天才じゃない」
※児玉光雄 著書『イチロー流 準備の極意』参照。
これを、「天才の弱点」としてコメントをされていた。
同じことはビジネスでも言える。上記のオウンドメディアの経験者も仮に天才であっても天才であるが故に「説明できない」と、相手に伝わらず、納得を得るのは難しいだろう。
スキルの抽象化とは、自分のやり方を整理し、他でも通用するようにまとめたものである。
なんとなく、ではなく、どこでも使えるものであり、その理由も語れる必要がある。
自身のスキルを具体化するスキルも大切!
さて、抽象化した自身のスキルを状況に応じて「具体的に説明する」ことも重要だ。
なぜなら、
・抽象化したスキルはわかりにくいこともあり、ピンとこない
→具体的な例が、話している受け手の状況と合致しているとイメージしやすく、説得力が出る
からだ。
例えば、上記の例で、
受け手が、
「オウンドメディアでSEO対策っていうけどさぁ、うちの場合は、女性向けのアンチエイジング用サプリメントを販売していて、競合が有象無象にいるんだよね。
こんなんでSEOなんて成果あるの?」
となった時に、
近い具体例を出して、
「私が手掛けた例で、Dサプリ株式会社という会社があり、そこではアンチエイジングというキーワードは競合が多すぎて新規で狙うにはハードルが高かったので、●●、△△といったこの会社に合うミドルキーワードを探し出して対策をしたことにより、SEO対策中心で●●万のユニークユーザー数になったという例がありました。」
と、抽象化したスキルの具体例・実績を挙げられれば、イメージしやすく、刺さりやすいだろう。
上記のスキルの抽象化、具体化といった伝え方の話はともすれば「コミュニケーションスキル」「プレゼン能力」でまとめられてしまいそうだ。
が、本当に仕事を獲得できているプロ人材、もしくは営業マンは、単純なコミュニケーションスキルだけでなく、抽象化と具体化の使い分けができている。
上記は個人の場合のスキルのトーク例であるが、企業での営業もまったく同じではないだろうか。
営業マンの話も抽象化され再現性があり、具体的で納得性があれば購入しやすい。
僕も「雇用する側」としても、面接や商談等で確認用に使っているので、経営者や人事部の方は、面接でも質問として活用できるかもしれない。
日々さまざまな売り込みに沢山の企業あるいは転職等の個人も訪問がある場合は、「再現性があるか」「イメージも具体的にできるか」を判断軸の1つとしても良いのではないだろうか。
誰しも、人生数回、「これはピンチ!」という時がある。
「いざという時に」頼りになるのは、自分自身。
そんな時にスキルで収入を得るのに大切な法則は、
・需要が多く、供給が少ない分野のスキルを磨こう
・スキルの抽象化、具体化の使い分けをできるようにしておこう
ということ。
逆に、経営側、採用側は、そのスキルは「再現性があるのか」「イメージできるか」を中心に質問していくと、その営業マンや採用されたい個人が報酬に値するか見分けられる可能性が高くなる。
企業・採用担当者の
みなさまへ
CARRY MEでは、年収600-1000万円レベルのプロ人材を
「正社員採用よりもコストを圧倒的に抑えながら」
「必要な時に、必要なボリュームで(出社もOK!)」
「最短1週間の採用期間で」
ご紹介いたします。

![CARRY ME [キャリーミー] |個人のプロに仕事が舞い込むサイト](https://carryme.jp/magazine/wp-content/themes/carryme/common/images/cta_bt01.png)