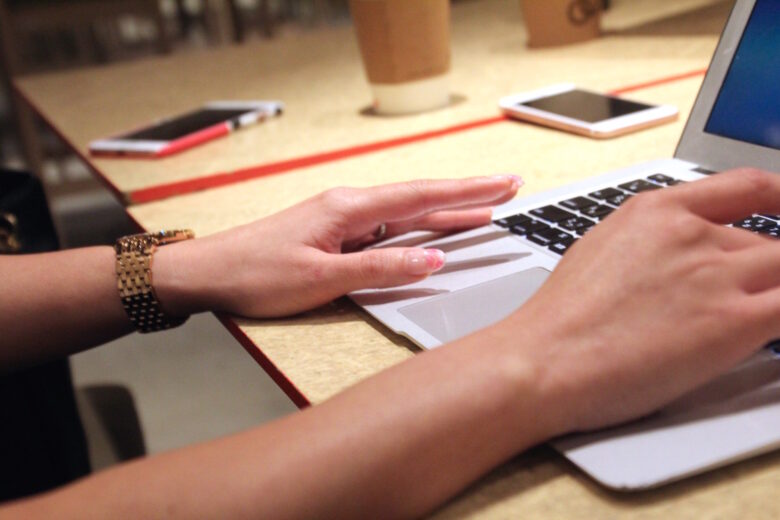【アルバイトの不祥事対策】バイトテロ・バカッター時代に求められる労務管理とは?
2019/2/19
とりあえず見てみない?プロ人材リスト
- 30人以上のあらゆる施策の上位5%プロ人材をご紹介!
- 貴社にマッチする最適なプロ人材が間違いなく見つかる!
- プロ人材の職種/経歴/実績など、詳細な人材をまとめて解説!
目次
バカッター・バイトテロとは?アルバイトの不祥事は対策を取るべきリスク
連日、飲食店によるアルバイトによる不適切行為、通称「バイトテロ」が大きくメディアで報道されています。「バイトテロ」を通じて、アルバイトが面白半分に企業内で不適切行為を行い、YoutubeやTwitterなどのSNSに投稿することで、不適切行為が世間に拡散されメディア等で大きく報道されてしまうと、企業の信頼は失墜していまい経営にも大きな影響が出てしまいます。
こうした悪ふざけはこれまでも表沙汰にならないだけで、企業内部で行われることはあったかもしれません。しかし、インターネット社会でこれだけSNSが浸透している昨今では、このような悪ふざけが表沙汰になってしまう環境が十分すぎるほど整っており、私たちの目に留まりやすくなっています。
企業にとっては、単なる悪ふざけではなく「バイトテロ」=「経営をゆるがすリスク」という認識を持つ必要性が増しています。
なぜアルバイトが不祥事を起こすのか?アルバイトの労務管理の必要性
そもそも、不適切行為はアルバイトだけが起こすものではありません。正社員によっても不適切行為や不祥事はもちろん行われる場合はあります。しかし昨今アルバイトがこうした不適切行為を起こすことが多くなっているのはどうしてなのでしょうか。
企業への帰属意識と契約期間
やはり無期雇用が前提の正社員に比べると、アルバイトについては「一時的な仕事」という意識を持っている場合が多いように思います。
有期雇用で労働時間の短いアルバイトだと、どうしても企業への帰属意識は薄まる傾向にあるように思います。「学生アルバイトが無断で急に会社に来なくなった」というご相談を企業からいただくことが実は少なくありませんが、他方、正社員が無断で来なくなるケースは私の経験上では滅多にありません。
「いつかは辞める一時的な仕事」という意識・帰属意識の欠如は一つ理由としてはあるように考えています。
「契約期間があるからいいか」という企業側の慢心
一般的な日本企業における正社員とは、無期雇用です。企業にとって、契約期間のない無期雇用社員は日本の労働法では解雇が難しいということもあり、その雇用管理は有期雇用者の労務管理方法に比べ、しっかりしたものを持っている企業が多くなっています。
例えば、後に詳述しますが、正社員用の就業規則はほとんどの企業が策定していますが、アルバイト用の就業規則はない場合が多くみられます。そして就業規則には守って欲しい服務規律が何項目も羅列されており、またそうした服務規律を守らなかった場合の懲戒事由なども細かく定めています。
一方で、アルバイトについては有期雇用であることも手伝ってか、「最悪契約期間満了で辞めさせられる」というような企業側の慢心もあり、正社員に対しては厳しく規律を設けていたとしても、アルバイトにはなぜか緩やかな運用をしているということが多々あるように考えています。
まさに正社員といえば日本型の「メンバーシップ型雇用」つまり「その企業の一員という意識を高く持て!」というロイヤリティ重視の労務管理体制をとっているところも、アルバイトにはなんとなく甘い、なあなあな労務管理をしているということは多くの企業で心当たりがあるところではないでしょうか。
バカッター・バイトテロを防ぐ対策、企業防衛型の労務管理とは
現在は深刻な人手不足もあり、「フルタイム・残業可」というような一般的な正社員を雇用することが難しくなっています。また、日本全体の就労人口も減少している中で、今後企業としては、育児・介護中の方、障害のある方、シニアの方など、「フルタイムは難しいけれど、空いている時間で働いてもらえる方」の活用は避けて通れない課題です。
これまでは「正社員=ノーマル、アルバイトなどの有期雇用=臨時的な雇用の調整弁」というこれまでの考え方でしたが、こうした考え方が根本的に崩れていく可能性があります。主戦力としてアルバイトの活用が進んでいる、という流れで、アルバイトの労務管理は、「バイトテロ」のみならず重要になってきていると言えるでしょう。
では企業の労務リスク防衛の観点から、アルバイトの労務管理とは具体的にはどのように構築していけばよいのでしょうか。
アルバイトにもルールの整備を
先に述べたように、正社員用の就業規則はあっても、アルバイト用の就業規則はないという企業が多いように思います。
現在は、正社員用の就業規則の中で、「アルバイトは、本就業規則は適用せず個別の定めによる」として、アルバイトは個別の雇用契約書でその労働条件を決めるという手法が多くとられています。
一方服務規律や懲戒事由のようにアルバイトにも守って欲しいことは、「正社員就業規則を適用する」と雇用契約書内に記載して、適用させたい部分のみを正社員就業規則に飛ばすという作りになっていることが多いように考えています。
こうした運用がとられている理由としては、単純にアルバイト用の就業規則を策定する手間やコストの問題に加え、法令上も「アルバイト用の就業規則を作りなさい」という義務があるわけではないからです。
(労働基準法では10人以上の労働者がいる場合に就業規則の策定義務はありますが、この10人のカウントには正社員だけではなくアルバイトなども含んでいます。つまり、就業規則を個別にわけて作れというような要請は法的にされていません。)
しかし、この方法だと、わざわざ正社員用の就業規則を読むというアルバイトがどれだけいるかという疑問があります。「このような不祥事をすると、このような懲戒処分もあって、さらには損害賠償も免れないですよ」ということをアルバイトの方にも理解し、規律をもって行動してもらう必要があります。
アルバイト用の就業規則を作って採用時にお渡しすることが一番確実ではありますが、コストがかけられないという場合には、アルバイトが適用される正社員用の服務規律や懲戒などの就業規則条文部分を印刷して、採用の際に渡して説明するということだけでも効果はあるように思います。こうした対応をすることで、企業としてもなにか不祥事があった場合の管理責任を問われた際に、「アルバイトにも不祥事を起こしてはならないという教育を施していたのだ」と主張ができますし、企業の責任の度合も低減します。
よりマイルドな“誓約書”という手も
また、実例ですが、最近弊社の顧問先のアルコール飲料を製造・販売する企業が、醸造所で未成年の学生のアルバイトを新たに雇用するというケースがありました。 仕事の中で日々アルコールに接する機会が多いということが、バイトテロ・労務リスクが高いと考え、「バイト中に飲酒をするなどの不適切行為はしません。」等を記述した誓約書をアルバイトから取得してもらったケースがあります。
就業規則の策定が難しい場合でもこうした誓約書を別途受領するというだけで、アルバイト側の意識も変わりますし、企業の労務リスク防衛の観点からも効果があると考えています。 今、アルバイトには服務規律もなければ懲戒条文の適用もないといった企業の場合、このような事項を盛り込んだものを誓約書として作成して取得するということも有効だと考えます。
また、昨今のバイトテロのニュースを見て感じることですが、不適切行為を実際に行う者の他に、それを動画に収める者がいるという事実も無視できません。
「他人を唆し、共謀し、又は他人に手を貸して助けたり隠ぺいした場合にも同様に懲戒の対象とする」「不適切行為が未遂におわってもその責を逃れることができない」といった、内容を就業規則や誓約書に盛り込み、自分が実際の不適切行為の実施者でなくとも、処罰の対象となるのだというようなことを理解させたいところです。
バカッター・バイトテロ対策にはアルバイトの労務管理とともに信頼関係が大切!
述べてきたように、旧来型のアルバイトへの労務管理だと労務リスクの観点から不十分なケースが増えてきています。「バイトテロを防ぐための企業防衛型の労務管理とは」で述べたように、労務管理上、就業規則や誓約書を取得してアルバイトへの教育を行うということはバイトテロ防止にダイレクトに効果があるものだと考えていますが、「そもそものアルバイトの労働環境が劣悪になっていないか?賃金水準は適当か?」というアルバイトの労働環境を今一度振り返って考えてみることが必要だと思います。
アルバイトが誇りとモチベーションをもって働けるような職場環境であれば、こうしたバイトテロのリスクは劇的に低減すると考えています。 バイトテロを起こす側が悪いということは、それはもちろんそうです。しかし、常日頃からアルバイトとの信頼関係を構築するということが、企業の成長にとってなによりも重要なことですし、そこに一定のルールを構築しておくことは現代の企業の責務なのです。
キャリーミーはマーケティング・広報領域を中心にプロ人材を紹介しています!
- 中途採用では出会えない優秀な人材が自社のメンバーに!
- 戦略から実務まで対応、社員の育成など業務内容を柔軟に相談!
- 平日日中の稼働や出社も可能!
この記事を書いた人

- 寺島 有紀
寺島戦略社会保険労務士事務所 所長 社会保険労務士。
一橋大学商学部 卒業。
新卒で楽天株式会社に入社後、社内規程策定、国内・海外子会社等へのローカライズ・適用などの内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。在職中に社会保険労務士国家試験に合格後、社会保険労務士事務所に勤務し、ベンチャー・中小企業から一部上場企業まで国内労働法改正対応や海外進出企業の労務アドバイザリー等に従事。
現在は、社会保険労務士としてベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行っている。
2019年4月に、「これだけは知っておきたい! スタートアップ・ベンチャー企業の労務管理――初めての従業員雇用からIPO準備期の労務コンプライアンスまで この一冊でやさしく理解できる!」を上梓。
寺島戦略社会保険労務士事務所HP: https://www.terashima-sr.com/
2020年9月15日、「IPOをめざす起業のしかた・経営のポイント いちばん最初に読む本」(アニモ出版)が発売されました。
その他: 2020年7月3日に「Q&Aでわかる テレワークの労務・法務・情報セキュリティ」が発売されました。代表寺島は第1章労務パートを執筆しています。