キャリーミーでプロとしてのキャリアが広がる

ホーム > キャリーミー創業ストーリー > 5章 夜明け前の奔走 ~キャリーミーのビジネスモデル進化~

5章 夜明け前の奔走 ~キャリーミーのビジネスモデル進化~
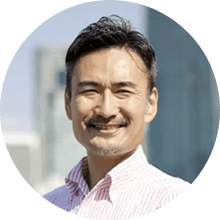
大澤亮
1972年、愛知県生まれ。早稲田大学時代に両親から留学に反対され、自腹で米国に留学(カリフォルニア州立大学サンバーナーディーノ校→ U.C.バークレー)
2009年、株式会社Piece to Peaceを創業し代表取締役に就任。2016年、プロ人材による課題解決事業“CARRY ME(キャリーミー)“を創業。
「恩人」システムシェアード・徐社長との出会い
1号社員と2号社員の退職、信頼していたプロ人材A氏の裏切り、外部からの厳しい指摘──。続けざまの組織トラブルに、私は経営者としての未熟さを痛感させられた。だが同時に、キャリーミーのミッション・ビジョン・バリューを明文化し、組織に浸透させる必要性を強く感じ始めていた。
「私たちは単なる人材紹介屋ではない。クライアントに寄り添い、成果に導く“課題解決パートナー”であるべきだ」
その確信が、苦境の中で少しずつ形になりつつあった。
そんな中、2017年11月、ある出会いが一筋の光となって差し込んできた。「どんな素人でも必ず活躍できるSEになれる」とSEの教育に定評のある株式会社システムシェアード・徐日柱(ジョ・イルチュ)社長との出会いである。きっかけは、代理店的な動きをしてくれていた会社を通じたウェブフォームからの問い合わせだった。当時のキャリーミーは、債務超過こそ脱していたが、いつ資金が尽きてもおかしくない状態。営業として私が先方に出向き、応対したのは人事部長だった。会社情報に売上や利益を記載する欄があり、「これはもうダメかもしれない」と、内心諦めかけた。
同社は当時でもすでに100億円をゆうに超える売上を誇っている、成長優良企業、こちらはつい先日まで債務超過だった、いつ倒産してもおかしくないレベルの会社である。
ところが予想に反して先方は興味を示し、後日、徐社長との面談が決まった。
秋葉原のシステムシェアード社を訪れた私は「成長企業の社長=厳しいタイプ」という勝手な先入観で身構えていた。しかし、目の前に現れた徐社長は、穏やかな笑みを浮かべ、物腰も柔らかい人物だった。そのギャップに思わず拍子抜けしたほどだ。

▲徐日柱社長
「プロ人材、ですか。初めて聞きましたね」
徐社長は私のたどたどしい説明にも真摯に耳を傾け、身を乗り出しては質問を重ねてくれた。頭ごなしの否定も、試すような圧も一切なかった。
「なるほど。優秀な人ほど独立する。そんなフリーランスや起業家の方に、業務委託で力を借りる。面白いコンセプトですね」
その一言に、私は思わず息をついた。暗闇に灯った小さな明かりのようだった。
2度目の商談でも、徐社長は変わらず穏やかな笑顔を浮かべながら、冗談めかしてこう言った。
「会うのは、無料なんでしょ?」
その言葉に場が少し和みつつも、彼の目は真剣だった。「プロ人材」という仕組みに対する関心は明らかに高まっていた。
「大澤さんのところでは、どういうプロがいらっしゃるんですか?」
「はい、例えば営業分野ですと、こういった実績を持つ者がおります」
私は事前に用意していたプロ人材のプロフィール資料を取り出し、数名を紹介した。単なるスキルの羅列ではなく、彼らがいかに「成果」にコミットしているか。その点を何よりも強調した。
「なるほど……一度、会ってみましょうか」
徐社長はそう言って、営業のプロ人材一人との面談をその場で決めてくれた。即決というわけではなかったが、それでも私にとっては大きな前進だった。当時は、社長クラスと直接商談できる機会すら貴重であり、プロ人材との面談へと繋がったことは希望の兆しだった。
徐社長が面談をしてくれたのは60代の男性。キャリーミーの得意とする30代〜40代の中堅どころではないが、元マイクロソフトの営業部長でMBA保有者という輝かしい経歴の持ち主。しかも、最先端の「IT業界での営業」について豊富な知見も保有し、「泥臭い営業」も知り尽くしていた。面談で少し検討していた徐社長だったが、面談後はプロ人材として即採用に至った。
この男性はたまたま、慶応のビジネススクール(大学院)の大先輩で、人として信頼している存在だったが、徐社長はのちに「衝撃的な存在だった」と振り返ってくれた。
なぜなら、営業ノウハウを惜しみなく提供してくれたり、自身でも営業の手本を示してくれて、システムシェアードの営業社員たちのロールモデルになってくれたのだ。さらには若手を率いて飲みに連れて行くなど、契約上の稼働など関係なく「GIVE」のマインドで接してくれた。
評価も上がり、成果も上がった結果、システムシェアード社は営業分野で計4名のプロ人材を継続的に活用してくれるようになった。中途採用では出会えない即戦力人材を、必要な時期に必要な形で活用できる。業務委託ならではの柔軟性とプロ人材の質の高さが評価されたのだろう。
それから数カ月後、徐社長から一通のメールが届いた。
「今回、サービスをはじめてご利用させて頂いてますが、正直、なんという素晴らしいサービスを作って頂いたんだろうと感動しております。私たちの今後の課題やニーズにとてもマッチします。今後実現したいビジョンとのギャップを埋めるのに御社のサービスが凄い必要となります」
(2018年1月26日徐社長より)
その文面を目にした瞬間、私は一瞬、息を呑んだ。心が震えた。債務超過、父の拒絶、免許の剥奪、仲間の離脱、そして自身の健康問題──。これまで何度「もう無理かもしれない」と感じただろう。それでも、決して諦めなかった自分を少しだけ認めたくなった。
プリントアウトしたそのメールを、毛利や布井といった信頼する仲間たちに見せた。
「僕たちのやっていることは、間違っていなかったんだ!」
喜びというより、静かな確信が胸を満たした。皆の顔に、心の底からの安堵と希望が浮かんでいた。
徐社長からのこの一通のメールは、私たちにとってただの感謝の言葉ではなかった。それは暗闇の中でもがいてきたキャリーミーにとって、確かに夜明けを告げる狼煙のようなものだった。
約1か月後には現場を仕切る田窪部長(当時)からもこのようなメールを頂いた。
「本当に有り難い数ヶ月でした。皆さん本当にプロで、仕事が嘘のように進む進む、、、笑 感謝でいっぱいです。もしできましたら、現場の声を定期的におとどけしたいので、頻度はお任せしますが遊びにいらしてください!できましたら2ヶ月に一回はお願いしたく、また進んでいてヒントや相談、増員などの際に温度感をシェアできますと幸いです」
(2018年3月2日 田窪部長(現在は執行役員)より
「直接契約型」から「サブスクモデル」への進化
この取引は単なる売上という短期的成果にとどまらず、キャリーミーのビジネスモデルを根本から見つめ直すきっかけともなっていった。
当初、システムシェアード社はプロ人材一人当たり70万円の紹介料を支払う「直接契約型」の形式を採用していた。これが複数件続き、一時的にまとまった収益が入ったのは事実だ。
だが、私はすぐに「これは違う」と直感した。
70万円という価格は、プロ人材が持つ本来の価値に見合っていない。何より、この形では一度きりの取引で終わってしまい、継続的な信頼関係も本質的な「課題解決」も生まれにくい。私たちが目指すのは、そんな浅い関係ではない。
「これではただの人材紹介屋だ。僕らがなりたいのは、それじゃない」
そう自分に言い聞かせるようにして、私はビジネスモデルの転換を決断した。プロ人材とキャリーミーが契約し、キャリーミーが企業と業務委託契約を結ぶ「再委託型」を基本とし、それを月額課金の「サブスクモデル」へと進化させることにしたのだ。
このモデルなら企業が抱える課題を解決し続ける限り、私たちも継続して価値を提供し続けられる。クライアントと同じ方向を見据え、成果を共に追いかける──。そんな長期的な関係こそが、真の「課題解決パートナー」ではないかと確信していた。
「真のプロ人材」を厳選する三つの柱
この取り組みは、同時に「プロ人材とは何か」という本質的な問いに向き合う機会にもなった。ある日、徐社長がこう尋ねたのだ。
「大澤さん、どうやってこんな優秀な人たちを集めて審査してるんですか?」
その問いに答えるうちに、実際に活躍するプロ人材の姿を見る中で、私たちは社内で議論を重ねた。成果を出し続けられる「真のプロ人材」とは何か。導き出された答えは、三つの柱だった。
「専門スキル」
「コミュニケーション能力」
「成果へのコミットメント」
この定義に基づき、私たちは「質」を担保するための三段階審査体制を構築した。登録時のキャリアアドバイザー(CA)面談、企業担当者同席の三者面談、稼働後のフィードバック。もともとリスク回避のために始めた三者面談は、やがて企業の本質的な課題を吸い上げ、プロ人材の適性を深く理解する場へと進化した。
この仕組みで蓄積された「審査済みプロ人材」のデータベースは、やがてキャリーミーの競争優位性そのものとなっていった。
思い返せば、懇意にしている経営者からいただいた「サービスが使いにくい」という厳しい声も、この転換期に大きなヒントとなっていた。単に「優秀な人がいますよ」と紹介するだけでは足りない。クライアントが抱える課題を丁寧に聞き取り、それをどう分解し、どのプロ人材で、どのように解決するのか──。その「交通整理」まで含めて、初めて安心して新しい仕組みを使ってもらえるのだ。
私たちはようやく「紹介屋」の枠を超え、真にクライアントの課題と向き合う「解決のパートナー」へと進化を始めていた。
その後、課題解決パートナーとして、システムシェアード社との取引はさらに加速し、10人、15人、20人と活用が進んでいった。
人事部の松山部長からは以下のようなコメントも頂くようになった。
「プロが課題に対して業務切り分けを適切に行い、それにあわせたプロ人材をキャリーミーにご紹介いただいたので、プロ人材活用が更に進んだ」「社内では育成・採用できないような、経験やスキルを持ったプロ人材にアサインしてもらった。彼らに本音で相談できたから、会社経営で非常に重要なポジションをお願いできた」「特に人事のプロ2名、経営管理アドバイザーとの出会いは大きかった。自分以上に人事に詳しい人間が社内におらず、相談相手がいなかったが、プロ人材は私と同じ目線で動いてくれていた。部下や経営層に言いづらい相談でも、プロ人材には相談出来、本当に助けられた」

▲松山部長
こうしたコメントを自ら掲載するのは、いささか手前味噌だとはわかっている。だがしかし、債務超過を経験した会社の代表としては感無量だったという気持ちを記録しておくためにも敢えて掲載した。キャリーミーのビジネスモデルの「ファーストペンギン」になっていただいた徐社長とシステムシェアードの皆さんには、どれだけ感謝してもしきれないのだ。
この頃、社会の流れも追い風となって吹き始めていた。2017年から2018年にかけて政府が掲げた「働き方改革」。副業解禁が加速し、世の中に「複業」「フリーランス」というキーワードが定着し始めたのだ。
「これは、間違いなく市場が来る」
胸が高鳴った。私たちがゼロから立ち上げた「プロ人材」という新しい市場が、にわかに熱を帯び始めていた。だが、それは同時に競合の出現という脅威の始まりでもあった。
「この市場は自分たちがリードし、育てていく」
その覚悟は、もう揺るぎのないものになった。内側の痛みも外からの指摘も、すべてを糧として私たちは前に進んできた。ようやくビジネスモデルは形を成し、サービスの質も高まった。
風は確かにこちらに吹いている。だが、それでもまだ道のりは遠い。組織の基盤は、盤石とは言い難い。だからこそ私は次に踏み出すべきだと決意した。
それが「本格的な資金調達」への挑戦だった。
キャリーミーが、次のステージへと駆け上がるために。
【6章へ続く】
編集協力・木村公洋