キャリーミーでプロとしてのキャリアが広がる

ホーム > キャリーミー創業ストーリー > 1章 挑戦を許されなかった少年

1章 挑戦を許されなかった少年
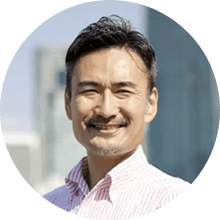
大澤亮
1972年、愛知県生まれ。早稲田大学時代に両親から留学に反対され、自腹で米国に留学(カリフォルニア州立大学サンバーナーディーノ校→ U.C.バークレー)
2009年、株式会社Piece to Peaceを創業し代表取締役に就任。2016年、プロ人材による課題解決事業“CARRY ME(キャリーミー)“を創業。
「挑戦なんて、するもんじゃない」
それが、父の口癖だった。
静かな、しかし妙な重みのある声。挑戦は悪で、夢は人生の遠回りだとでも言うように。何かを始めようとすれば「そんなことをして何になる」「余計なことはするな」と、目の前のドアが閉ざされる感覚。
父は、挑戦の——いや、挑戦しようとする“気配”そのものを憎んでいた。
時にそれは、心配を装った。
「黙って言われた通りにしろ」
「大企業に入れば安泰なんだ」
挑戦は道を踏み外すこと。レールを外れるのは“落ちること”だと教え込まれた。だが、そのレールの上にいるほど、心が離れていく。いつしか私は、挑戦を口にしなくなった。心の奥の叫びとは裏腹に。
「違う。これは、本当の自分の人生じゃない…!」
“違い”が肯定される国、アメリカ
3歳で、父の仕事によりカリフォルニアへ渡った。何もかもが大きく、眩しい世界。英語も話せないまま現地のキンダーガーデン(幼稚園)に放り込まれたが、不思議と怖くはなかった。言葉の通じないアジア人の私にも、まわりの子は笑顔で接し、先生は小さな成功を見つけては「Great!」と褒めてくれた。できなくても責められず、「違い」が「ダメ」にならない。その肯定的な空気に、私は初めて触れた。
だが、5歳で帰国した途端、すべては反転した。日本の幼稚園では、言葉がうまく聞き取れない、うまく話せない。「この子、知恵遅れじゃないかしら」と先生に言われたと、両親から聞かされた。日本では「違う」ことが不安の種になる。“自分は変なんだ”と初めて意識した瞬間だった。
以来、私は自分を日本の“枠”に押し込めた。アメリカの記憶は、遠い夢のように薄れていった。
父のルール、母の沈黙
我が家の食卓では誰も言葉を発さない。父が「いただきます」と言うまで、誰も箸をつけない。聞こえるのは食器の音と、父が味噌汁をすする音だけ。誰もが息を殺し、父の「親の言うことを聞いていればいい」という無言の圧力を感じていた。
安定を好み、「レールから外れること」を嫌う父は、明治大学を出て中小企業に就職。希望した早稲田大学に入れず、大手企業にも就けなかった過去への悔しさの裏返しだったのかもしれない。「早稲田以上に行け」。それは応援ではなく、父自身の満たされなかった願望の押し付けだった。
「挑戦なんて、するもんじゃない」——その言葉の奥にある父の痛みと恐れを感じつつも、私はそのレールに乗りきれない違和感を覚えていた。
そんな父が唯一金を惜しまなかったのは、ゴルフと車だ。会員権を買い、週末はゴルフ三昧。車は頻繁に買い替えた。
対照的に、家族への出費は極端に切り詰めた。中学まで風呂は三日に一度。新城市の実家以外の旅行はおろか、外食も論外だった。
「電気がもったいない」
「電話代が高すぎる」
「毎日風呂なんて論外だ!」
特に苦痛だったのは、実家への車中だ。父の煙草の煙と排気ガスが充満し、車酔いと重なって何度も吐いた。母も兄も、父に何も言えなかった。ハラスメントという言葉もない時代、それが「普通」だったのかもしれない。
些細なことでも小言が飛んでくる。だから私はお年玉も使わず、言いたいことも言わず、父の顔色を“察する”ようになった。自分の気持ちより、空気を読むことが生存戦略だった。
母は優しかったが、それは「何も言わない優しさ」だった。父に叱られても、挑戦を否定されても、母はただ黙っていた。助け舟は出ない。「お母さんはどう思う?」と聞いても、困ったように笑って「お父さんに相談してみるね」と言うだけ。テーブルの縁を指で叩く仕草だけが、母の内心を微かに語るようだった。
成長するにつれ、わかってしまった。この人は味方にはなってくれない。「自分には兄以外の味方がいない」。家の中で一人立つような、冷たい孤独感があった。
兄と絵画の存在と、「ルール」の壁
当時、私を救ってくれたのは兄と絵画だ。2つ上の兄は弟想いで、いつも私を庇ってくれた。唯一心を許せる存在だった。
そして、絵を描くこと。勉強はダメだったが、絵だけは得意で、小学生の時に区で表彰されたこともある。何より「何も考えずに没頭できる」時間だった。幼稚園の先生に「構図が面白い」と言われたらしい。人と同じようにできない「変わっていた」ことが、唯一評価された経験。それが今の「人と違う視点」に繋がっているのかもしれない。もっとも、その才能も受験勉強で左脳を鍛えるうちに失われ、中学以降は絵から遠ざかったが。
だから私は、自分の本音を心の奥にしまった。
「どうせ、誰にも届かない」
「言っても、何も変わらない」
それでも心の底では、母に「応援してるよ」と言ってほしかった。その一言があれば、どれほど救われただろう。母は「介入しないこと」で波風を立てずに生きていたのかもしれないが、私にはただ「遠い人」に感じられた。
兄は「神童」と呼ばれ、常に優秀だった。テストは満点、先生にも褒められ、父も兄には機嫌が良い。「なんで兄ちゃんみたいにできないんだ」「見習え」。その言葉は「お前はダメだ」という烙印だった。兄を尊敬しているが、自分も同じようになれる気はしない。いつしか“比べられない領域”を探すようになった。
兄の「才能」と私の「未完成」は、常に家の中で対比された。神童と呼ばれた兄は、高校受験で早稲田・慶應の付属に全て合格し、慶應高校へ進んだ。その結果、「期待されていない」はずの私へのプレッシャーは、逆に増していった。
兄と比べられる息苦しさ。「どうせ勝てない」という前提。それが皮肉にも、自分なりの挑戦への“静かなエンジン”になっていったのかもしれない。「このままじゃ終わらせたくない」「“自分だけの挑戦”を見つけたい」——心の奥で、そんな思いが静かにくすぶっていた。
挑戦を阻むのは、家庭だけではなかった。小学生の頃、私は他の子より頭一つ背が高く、6年生で172センチに達した。大人びた体格と顔立ちのせいで、ランドセルが似合わず恥ずかしかった。「違うバッグで通学したい」と訴えても、「ルールだから」「みんなそうしているから」と一蹴された。個性や感情は認められない。窮屈だった。
近所の床屋では小学生料金では散髪してくれず、「高校生ですか?」と聞かれて毎回、年上の料金を請求された。家庭の外でも、「なぜ?」と問えば「ルールだから」という壁にぶつかる。その繰り返しが「ならば、ルールを作る側に回りたい」という思いを育てたのかもしれない。
とはいえ、自己肯定感のない当時の私に、そんな力はなかった。「大人が決めたルール」に従うしかなかったのだ。
“本当の人生”への渇望
高校に入り、ほんの少しだけ風向きが変わった。早稲田大学高等学院。偏差値72の進学校に、まぐれのように合格できたのだ。周りは優秀だったが、話してみると絶望的な差があるわけではない。
「僕だって、やればできるんじゃないか」
そんな感覚が、小さな種火のように胸の奥で灯り始めた。
だが、友人たちが「安定」や「無難さ」で進路を選ぶのを見て、自分だけがそこに馴染めない孤独を感じた。
「親が望む“正しいルート”をなぞるのが、本当に自分の人生なのか?」
家に帰れば、息の詰まる日常が待っている。
「余計なことはするな」
「レールの上を歩け」。
それどころか父は学部まで指定してきた。「大学は早稲田大学の商学部より偏差値が高いところでないと行かせない」。学費は祖父母が出してくれるというのに、「金は出さないが口は出す」。その矛盾に、高校生になった私は「自由と責任」について考えざるを得なかった。(後に留学先で一人考えたとき、そんな両親に対しても、育ててくれたことへの感謝が湧いてきたのだが、当時の私には、ただやるせなさしかなかった。)
父の言葉が呪文のように響く。挑戦するな。夢を見るな。失敗するな。外で灯った希望の火が、家で消えそうになる。
だが、もう完全には戻れなかった。高校で感じた手応えが「もっと違う世界を見たい」という渇望に変わっていた。このまま決められた未来を歩くことに、強い違和感があった。失敗してもいい。自分の意志で選びたい。挑戦したい。
そのとき蘇ったのが幼い頃にカリフォルニアで感じた、あの自由な空気だった。言葉も文化も通じなくても、笑顔で受け入れられた場所。「できないこと」ではなく「できたこと」を褒めてくれた先生。私の存在は、そこでは否定されなかった。
あの肯定的な空気の中でもう一度生きてみたい。思えばアメリカでの短い時間こそが、私の中の「挑戦」の原点だったのかもしれない。認められる心地よさ。否定されない安心感。「挑戦しても、叱られない場所があるはずだ」。その感覚が、心の奥底に残っていた。
まだ言葉にはなっていなかったが、静かに、しかし確実に、私は違う道を見つめ始めていた。自分だけの景色を歩きたいという欲求が、内側から膨らんでいた。「挑戦したい」という熱い火種が、父の言葉の壁の下で、間違いなく再び燃え始めていた。
ここまで読んで、「酷い父親だ」「さぞかし恨んでいるだろう」と思われるかもしれない。実際、ここに書けないような仕打ちや、今ならハラスメントと言われる言動も多々あった。
それでも、私には感謝しかない。貧しい風な家で育ったこと、不合理な厳しさを味わったこと。それが、今の私の精神的な強さの礎となっている。アフリカ駐在、複数回の起業や売却、債務超過…数々の試練を乗り越えられたのは、間違いなくこの経験のおかげだ。
全ての挑戦を否定され続けたことさえ、後の「リスクをとって挑戦しろ」という自身のミッションに気づかせてくれた。そう考えると、これもまた感謝でしかない。
「両親のおかげで今のキャリーミーがある」と言っても過言ではない。あらためて、「大感謝」である。
【2章へ続く】
編集協力・木村公洋